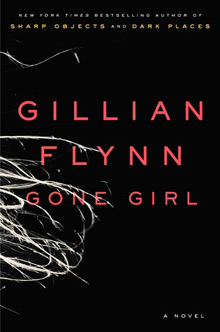ゴーン・ガール / ギリアン・フリン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (初出:) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
どうしようもないほどに徹底した非独創的社会のなかで
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
『冥闇』に続くギリアン・フリンの新作『ゴーン・ガール』の主人公は、ともに30代のニックとエイミーという夫婦だ。ふたりは5年前にニューヨークで出会い、夫婦になった。ニックは雑誌のライターで、エイミーは女性誌向けのクイズを作る仕事をしていた。ところが、経済危機や電子書籍の隆盛によって、夫婦はともに仕事を失ってしまう。 そこで2年前、ふたりはニックの故郷であるミズーリ州の町カーセッジに転居した。ニックの父親がアルツハイマー病に冒されているという事情もあった。しかし、都会育ちのエイミーにとって、田舎の生活は退屈きわまりないものだった。そして迎えた結婚5周年の日、エイミーが突然、謎の失踪を遂げる。家には争った形跡や血痕があり、確かなアリバイのない夫ニックに嫌疑がかけられる。 但し、これは前半部分を簡単にまとめた記述であって、独特の構成で綴られる物語には伏線らしきものが散りばめられている。前半では、ニックとエイミーそれぞれの視点の物語が交互に綴られる。 エイミーの物語は日記だ。それは当然、失踪以前の時間を扱っている。ふたりの出会いから、失踪直前に至る5年間の出来事や彼女の変化の断片が浮かび上がる。一方、ニックの物語は、妻の失踪直後から始まる。地元警察による捜査が始まり、ニックに不利な状況証拠が浮かび上がってくる。 だが、夫婦の物語でありながら、それぞれの物語のトーンはかみ合わない。どこかに嘘が紛れ込んでいるように感じられる。そして、後半に入ると、失踪の真相が明らかになる。だが、それだけでは物語は終わらない。予期せぬ出来事によって、前半の物語を支えていた土台が崩れ、主人公たちの関係が想像を絶するような変化を遂げることになる。 しかし、この小説の魅力は、二転三転する展開だけではない。前作の『冥闇』では、80年代の農家の苦境が重要な背景になっていた。ほぼ現代を扱っているといえる新作で、時代を象徴しているのは“デッドモール”だ。 ミシガン出身のバンド、フロンティア・ラッカスが2010年にリリースした『Deadmalls & Nightfalls』には、地元のWaterford Townshipにあったショッピングモール、Summit Place Mallの写真が使われていた。このモールは1963年に誕生し、2009年にその長い歴史に幕をおろした。ジャケットになっているのは、もう人のいないデッドモールの写真であり、このバンドはそれを時代の象徴として使っている。 フリンもこの小説で、デッドモールを細かく描写している。長い引用になるが、著者のこだわりがあらわれている部分なので、省略はしない(文中に出てくるマーゴは、ニックの双子の妹である)。 「一年前まで、カーセッジは<リバーウェイ・モール>という広大なショッピングモールに支えられた企業城下町だった。小さな町の人口の五分の一にあたる四千人もの人間がそこで雇用されていた。中西部全域からの集客をあてこんだ大規模モールとして、一九八五年に建設された。開店日のことはいまもよく覚えている。ぼくとマーゴ、母と父の四人で、だだっ広いコールタール舗装の駐車場に立ち、人だかりのいちばん後からにぎわいを眺めていた。どこかへ出かけると、父が決まって早めに帰りたがるからだ。野球の試合だえ、いつも出口のそばに陣取り、八回になると席を立った。マスタードまみれになり、日差しで身体をほてらせたぼくとマーゴは、いつも最後まで見せてもらえないと不満たらたらだった。でもこのときばかりは遠くから見ていて正解だった。開店イベントの全容を眺めることができたからだ。もどかしげに一歩ずつ前に進んでいく見物客たち。赤・白・青に彩られた演壇に立つ町長。消費主義という名の戦場のなか、ビニール張りの小切手帳とキルトのハンドバッグとで武装した兵士のぼくたちに、威勢のいい言葉が投げかけられた――誇り、成長、繁栄、成功。やがて扉が開いた。店内になだれこむと、エアコンの空気と、BGMと、にこやかに笑う店員たちに迎えられた。みな町の住人だった。その日ばかりは、父も店内に入り、行列に並ぶのを許してくれ、べたついたカップにたっぷり注がれたオレンジ・スムージーまで買ってくれた。 それから四半世紀、<リバーウェイ・モール>はあたりまえのようにそこにあった。やがて不況が襲い、モール内の店舗がひとつずつ消えていき、ついにモール全体が閉鎖された。いまでは十八万平米の廃墟と化している。再建に名乗りをあげる企業も、復活を約束する実業家も現れていない。モールをどうすべきか、大勢の元従業員たちがどうなるか、誰もわからずにいる。母も店舗のひとつの<シュー・ビー・ドゥー・ビー>靴店で働いていたひとりで、二十年ものあいだその店でひざまずき、揉み手をし、箱を選りわけ、汗ばんだ靴下を触らされてきたにもかかわらず、あっけなく職を失った」 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||