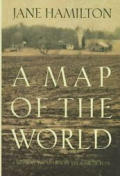サバービアの理想的な主婦像と表層や秩序に囚われたコミュニティ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (初出:「骰子/DICE」No.08、1995年2月、Edge of the World08、若干の加筆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ジョン・ウォーターズ監督の新作『シリアル・ママ』(94)とアメリカの女性作家ジェーン・ハミルトンの話題の新作長編『A Map of the World』(94)。前者は、サバービアを舞台にした血みどろのブラック・コメディであり、後者は、都市近郊にぽつんと残る酪農場を家族の楽園にすることを夢見る一家の苦難を描く長編だ。 ふたつの作品は、主人公や設定など、特に繋がりがあるようには見えないが、ある部分に注目してみると興味深い接点が浮かび上がる。どちらもサバービアの理想的な主婦像といえるものが鍵を握り、コミュニティや家族をめぐる危うい世界が描き出されているのだ。 ■■建前と本音をめぐり住民が自分で自分の首を絞める不条理■■ 『シリアル・ママ』の主人公は、キャスリーン・ターナー扮する主婦ビヴァリーだ。彼女は、ボルティモアのサバービアで、歯科医の夫とふたりの子供たちと典型的な郊外の生活を営んでいる。いや、表面的にそう見えるだけであって、本当は典型的どころではない。 潔癖で秩序が乱れることを許せない彼女は、ルールを守らない隣人たちに対する不満をつのらせる。そしてついには、ゴミを分別しなかったり、ショッピング・センターの駐車場で横入りしたり、レンタル・ビデオを巻き戻さないで返却する隣人たちを次々と血祭りにあげていく。 彼女の秩序や美観に対するこだわりというか、執念には、明らかにサバービアの理想が反映されている。たとえば、郊外のコミュニティは、町の腐敗のもとになる歓楽の要素を排除するために土地利用規制法を利用したり、統一された景観を保つために建築の基準を作ったり、美観を害す電線の類を地中に埋めたり、場合によっては、ガレージや壁の色に制約を設けるなど、結束して秩序や美観の維持に努めている。もちろん、家のなかもピカピカにしていることだろう。 皮肉な書き方をすれば、それは、表面がきれいであれば、そこに暮らす人間もきれいなのだと信じているような世界だ。しかし、理想は高く掲げたものの、人間にはやはり建前と本音がある。そうそうきれいごとばかりで生きていけるものではない。ウォーターズは、そんな世界に、住人たちの建前が作り上げたような“郊外の理想的な主婦”を登場させる。ということは、突き詰めれば、彼女によって血祭りにあげられる犠牲者たちは、自分で自分の首を絞めていることにもなる。 この映画を観ながら筆者が思い出すのは、ロング・アイランドのサバービアを舞台にしたハル・ハートリー監督の『トラスト・ミー』だ。主人公マシューの父親は、極端な潔癖症で、息子と顔を合わせるたびにトイレ掃除を命じる。そして、もうひとりの主人公マリアが町で出会う中年女性は、家がいつも清潔であることが虚しくて、もっと汚れていればいいと思うことがあると語る。彼らもまた、自分で自分の首を絞めている。 『シリアル・ママ』は、ビヴァリーを使って、そんな不条理を、不毛な日常における内的な苦痛や葛藤ではなく、連続殺人に具現化してしまう映画といっていいだろう。この映画のタイトルのシリアルには、朝食として食べられる“Cereal”と連続殺人鬼を意味する“Serial Killer ”がかけてあるのだが、これは単なる言葉遊びではないだろう。 そして、建前と本音が生む不条理を通してサバービアを挑発するウォーターズの狙いは、ビヴァリーの裁判となる後半でより鮮明になる。これは決して、キャスリーン・ターナーの捨て身の怪演を楽しむだけの映画ではない。 逮捕されたビヴァリーは裁判にかけられる。連続殺人の罪から逃れるには、精神異常を主張するしかないかに見えるが、彼女は、そうしようとする弁護士を解雇し、自分で弁護を開始する。こうして彼女の裁判は、証人席に座る彼女の隣人や警官と“郊外の理想的な主婦”のどちらが、陪審員たち心証に訴えることができるかを競うパフォーマンスの場となる。結局、ここでも証人たちは、郊外の建前のパワーに翻弄され、さらに自分の首を絞めていくことになるのである。 それでは、この理想の権化であるビヴァリーが守る自分の家族とはどんなものなのか。彼らはまるで、家族をターゲットにしたCMでも見せられているかのように、曖昧で薄っぺらなイメージのなかを生きている。もしかすると、それが、この映画のいちばん怖いところかもしれない。 ■■郊外の理想は家族が戻れる大地や自然を消し去っていく■■ 一方、ジェーン・ハミルトンの長編小説『A Map of the World』では、冒頭でも触れたように、アメリカ中西部のスモールタウンにぽつんと残された酪農場を購入し、家族の楽園を築こうとする一家が遭遇する苦難が描き出される。どうしてそんな作品が、郊外の家族や主婦と結びつくのかといえば、一家の酪農場の周囲は、宅地開発が進み、彼らがサバービアに包囲されているからなのだ。 主人公であるアリスと夫のハワードは、6年前にこの酪農場を購入し、いまでは、ふたりの娘と4人で暮らしている。周囲の郊外のコミュニティは、彼らを、自分たちで農場がやれると思い込んでいるヒッピーとみなし、最初からまったく交際をしようとはしなかった。 先ほど取り上げたのが『シリアル・ママ』だったから引用するわけではないが、たとえば、主人公夫婦と周囲の住人の関係は、アリスの視点を通してこんなふうに描かれている。 「ときおり住人たちは、肥やしの臭いや機械の騒音のことで苦情をいってきた。彼らが朝食のシリアルにかける体にいい白い液体と、目と鼻の先でガタガタやったり、悪臭をだすハワードの仕事の関係がわかっている人はごくわずかのようだった」 この文章には、臭いものや汚いものを排除する郊外の潔癖症がよく出ているといえる。 そんな孤立した状況のなかで、アリスには、様々なプレッシャーがかかってくる。酪農場の経営は決して楽なものではなく、彼女は、9月から6月までは、町の学校で保健師として働いていた。また、最近では、長女が癇癪を起こすようになり、育児に対しても自信を失いかけていた。そんな彼女の支えは、唯一付き合いのある隣人の一家で、同じようにふたりの幼い娘がいたため、母親同士が曜日を決めてお互いの娘たちを預かっていた。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||