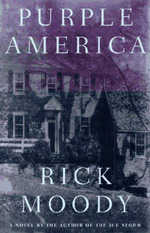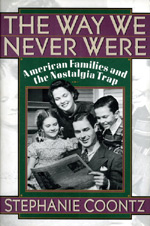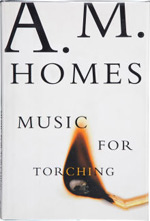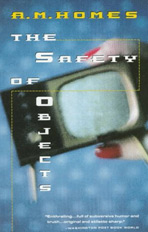中道化と個人主義のサバービアはどこに向かうのか |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (初出:「SWITCH」1999年9月号、Dr. Fact of Life49、若干の加筆) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
「アメリカを支配するサバービア――20世紀末、都市と郊外の関係を検証する」では、アメリカにおいてこの半世紀のあいだに都市と郊外の力関係が逆転し、90年代には、ついに増殖する郊外が政治まで動かす時代が到来したということを書いた。かつては、都市=リベラル、郊外=保守という図式が存在したが、現代の郊外にそれは当てはまらない。住人たちの多くは、保守、リベラルというイデオロギーに縛られることを嫌い、社会よりも自分の生活環境をコントロールすることに強い関心を持っている。要するに誰もが中道的で、しかも連帯することなく個々にそれなりの豊かさを求めているということだ。 それでは、小説家たちはこのような現実をどうとらえるのだろうか。現代の郊外を見つめ、そこから独自の世界を切り開くふたりの作家の作品に注目してみたい。 ■■リック・ムーディ 『Purple America』■■ まずはリック・ムーディの『アイス・ストーム』につづく長編『Purple America』。この作品は、その内容を説明すると、なぜここで取りあげるのか不思議に思われるかもしれない。物語が92年のある一日に限定され、そこから過去へと世界が広がることはあっても、現代が直接的に描かれることはないからだ。しかしこの作品には現代を考える上で重要なヴィジョンが埋め込まれている。 物語は、デクスター・レイトリフという30代半ばの男が、重い神経病のために全身が麻痺している彼の母親ビリーを風呂に入れているところから始まる。この母親は、コネチカット州の郊外に、二番目の夫であるルイス・スローンと暮らし、看護師に面倒をみてもらっている。92年のある週末、彼女はその看護師を休ませ、いまでは都市部に暮らしている息子のデクスターを家に呼び寄せる。それは息子に身の回りの世話をしてもらうためではなかった。 母親は息子に、彼の義父であるルイスが彼女を捨てて出ていったことを伝え、彼を呼んだ理由を明かす。彼女の神経病は重くなる一方で、全身が麻痺するばかりか、話したり考える能力も失われようとしていた。そんな彼女が出した答が安楽死だった。しかし彼女にはもはやひとりで死ぬ力が残されていない。そこで息子に協力を求めることにしたのだ。 デクスターは、自分が育った家に戻ってきたことで、自ずと過去が甦ってくる。それは決して幸福な過去ではない。一家は、デクスターが7歳のときに、貧困、犯罪、人種差別などの問題で揺れる都市を離れ、“50年代の楽園の理論”がいまだ健在の郊外へと転居した。母親は、家具や内装に自分の趣味を反映し、家を美しく保つことに情熱を注いだ。しかし、いまのデクスターは、その家が美しいとしても、絶対にそこに住みたくないと思う。 デクスター少年は、その保守的な郊外のなかで、両親の言いつけに従っていやいや教会に通い、いつしかドミノ理論や米ソ間の兵力均衡の重要性について熱っぽく語るタカ派的な思想の持ち主になっていた。彼は、若者たちが愛と平和のメッセージに熱狂する激動の時代に、愛国心を象徴するカーキ色のフランネルのズボンをはきつづけ、もうひとつの価値観に惹かれながらも、境界線を越えることができなかった。そんな過去に対する幻滅や喪失感から、彼はアル中になっていた。 ■■nuclear familyとnuclear weaponsというふたつの“核”■■ このデクスターの過去は、彼の家族の背景が明確になるに従ってさらに特別な意味を持つことになる。この家族の物語には、“核”が暗い影を落としている。39歳の若さで他界したデクスターの実父アレンは、マンハッタン計画(第二次大戦中の原子爆弾開発計画)に従事していた。彼は、核兵器の開発が軍人や一般市民を巻き添えにしたことに責任を感じ、被爆の後遺症で悲惨な死を遂げたのだ。 さらに、デクスターの義父ルイスは、地元の原子力発電所で働いている。その発電所は建造されてから25年のあいだに老朽化が進み、ルイスは、放射能がいつ漏れだすかもわからない危険があることを察知しているが、発電所の責任者はその事実を隠そうとしている。つまりこの小説では、ある一日のなかで、核家族(nuclear family)と核兵器(nuclear weapons)や原子力発電所(nuclear power plant)というふたつの核が、崩壊へと向かう過程が綴られることになる。 アメリカの小説でこのふたつの核を結びつけることは必ずしも珍しくないが、この小説ではその繋がりが鋭く掘り下げられ、物語に象徴的な意味をもたらしている。このふたつの核が持つ価値観は、もとをたどれば冷戦という共通の背景から生み出されている。核家族と冷戦の繋がりはわかりにくいかもしれないが、アメリカにとって、国民が共産主義思想に汚染されることを防ぐためには、所有や消費の楽しみを国民に植えつけることが近道だった。そこで、核家族を基盤とした50年代の幸福なアメリカン・ファミリーのイメージが作りあげられ、国民は郊外へと誘導されていったのだ。 ステファニー・クーンツの『家族という神話』では、50年代の家族像と冷戦の関係が以下のように記述されている。 「しかし、一九五〇年代の家族像が生まれた背景には、これよりももっと直接的なかたちでの抑圧があった。冷戦下の心理的不安感が、家庭生活におけるセクシュアリティの強化や商業主義社会に対する不安と混じり合った結果、ある専門家がジョージ・F・ケナンの対ソ封じ込め政策の家庭版と呼ぶ状況を生み出したのである。絶えず警戒を怠らない母親たちと「ノーマルな」家庭とが、国家転覆を企む者への防衛の「最前線」ということになり、反共主義者たちは、ノーマルではない家庭や性行動を国家反逆を目的とした犯罪とみなした。FBIやその他の政府機関が、破壊活動分子の調査という名目で、前例のない国家による個人のプライバシーの侵害を行った」 そうした事実を踏まえれば、この物語が象徴的に見えてくることだろう。デクスターの実父は、原子爆弾の開発に従事し、新しい核家族のなかで育ったデクスターは、冷戦のなかでタカ派の思想に染まり、自分を見失った。そして、冷戦構造が崩壊した後の92年、ふたつの核が崩壊へと向かっていくのである。 この物語は現代の郊外について考える上で重要なヴィジョンを提示している。なぜなら、もし郊外の幸福が冷戦の産物であるとするなら、冷戦の終結とともにその価値観が問い直される必要があるということになるからだ。しかしそのサバービアは、逆にイデオロギーだけを切り捨てて増殖をつづけ、アメリカの政治を動かすまでになっている。それはおかしなことだ。外的な要因によって作られた幸福な家族(のイメージ)が、その要因が消失しても、中身があるかのようにそこにあり、広がっているのだから。 ■■A・M・ホームズ 『Music for Torching』■■ そこで注目したいのが、A・M・ホームズの新作『Music for Torching』だ。彼女のこれまでの作品については「90年代のサバービアと家族を対照的な視点から掘り下げる」で触れているのでここでは省略するが、この新作では、まさに何のイデオロギーもなく、自分たちの生活環境をコントロールすることに強い関心を持つある夫婦の心理が、ホームズ独特の視点と感性で描きだされている。 ポールとエレインのワイス夫妻は、ふたりの息子に恵まれ、閑静なサバービアで理想的な生活を送っているように見える。しかし彼らは、退屈や欲求不満、わけのわからない苛立ちから、日常生活のなかで冗談とも本気ともつかない突飛な行動に出ることがある。たとえば、食事の片づけの最中に、セックスを迫ってきたポールにエレインが反射的にナイフで切りつけたり、ポールが突然、自分で頭を丸刈りにしたりするのだ。 |
|
|||||||||||||||||||||