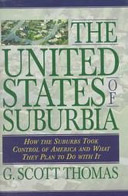アメリカを支配するサバービア |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| (初出:「SWITCH」1999年8月号、Dr. Fact of Life48、若干の加筆) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
■■サバービアがアメリカ大統領を決める時代の始まり■■ アメリカのサバービア(郊外住宅地)の生活や郊外化については、これまでにも様々な角度からこのテーマを掘り下げた小説やノンフィクションを紹介してきたが、今回は特に都市とサバービアの関係に注目してみたいと思う。第二次大戦後、冷戦と大量消費時代を背景に大規模な郊外化が始まってから半世紀を経たいま、21世紀を目前にして都市とサバービアの関係は、大きな変化を遂げようとしている。 G・スコット・トーマスの『The United States of Suburbia』では、この半世紀のあいだにサバービアがどのようにしてアメリカの政治を動かすようになり、新しい世紀に向かって社会をどう変えていこうとしているのかが描き出される。詳細なデータを駆使した研究書であり、郊外化が社会と政治に及ぼす多大な影響がはっきりと見えてくる。 本書の冒頭で著者は、96年の大統領選によって都市とサバービアの関係に決定的な変化が起こったという。伝統的に都市のリベラルやマイノリティの支持者を基盤としてきた民主党の候補クリントンが、その都市を無視し、サバービアの有権者をターゲットにして再選を果たしたからだ。 この戦略を打ちだしたクリントン陣営のブレーンによれば、それは票がどこにあるのかという単純な計算から生まれたという。大統領選は、定数538の選挙人リストの過半数である270を獲得すれば勝利することができるが、コンピュータの分析によれば、その時点でサバービアの有権者が多数を占め、実権を握る州が全米で23州あり、その選挙人枠を合計すると320に達していた。つまり、サバービアの州を押さえれば、勝利に必要な選挙人枠を確実に獲得することができるということだ。これは大統領を決める力が都市からサバービアに完全に移行したことを物語っている。 そこで本書ではこの半世紀のあいだに、都市とサバービアの関係がどう変化してきたのかが振り返られる。1940年のアメリカでは、大都市の周辺にすでにサバービアが存在していたが、白人の中流のほとんどは都市に集中して暮らし、都市が国家を動かしていた。ところが戦後の郊外化によって、共和党の支持層である白人の中流は続々とサバービアに流出し、そのかわりに南部の黒人、ヒスパニックやその他の移民たちが仕事を求めて大都市に流入し、民主党の支持基盤を作っていく。 その結果、サバービアが実権を握る州は確実に増加し、60年には17州を数える。その選挙人枠の合計は240で、明らかに大統領選への影響力を持ちはじめる。60年に6000万人を越えたサバービアの人口は、70年には7700万、80年には8900万人へと増加し、90年には1億人を突破する。一方、都市の人口はほとんど横ばい状態で、90年には4400万人。40年と90年の人口を比較すると、サバービアではその増加率が229%であるのに対して、都市は17%にとどまっている。 そこでクリントンは、92年の大統領選では、民主党が都市のリベラルやマイノリティにコントロールされているのではないことを有権者に印象づけた。しかしそれでも都市のマイノリティには選択の余地がなかった。共和党のブッシュ候補は最初から彼らを無視していたからだ。 96年の大統領選については冒頭で触れた通りだが、本書にはこの選挙戦について印象的なエピソードが紹介されている。それは、クリントンとドール候補がコネチカット州で初めて公開討論を行ったとき、両候補が取りあげた話題の内訳だ。彼らが口にした話題を頻度の高いものから順に列記すると、税金が59回、医療が26回、福祉が19回で、サバービアと深い繋がりのある話題が上位を占め、都市という言葉が出てきたのはたった3回だけだった。彼らは都市政策に関する討論を避け、まるでアメリカの大都市が一夜にして消失したかのようだったという。 そしてさらに本書を読み進むと、実際のところ、これからのアメリカを動かしていく世代にとって、都市は存在しないに等しいものであることがわかってくる。ベビーブーマー以後の世代は、サバービアで生まれ、そこで学校に通い、根本的に都市が人の生活する場所であるという認識を持っていない。彼らは、中心のないサバービアで育ったため、政治も含めて中心にコントロールされることを嫌う。民主党のリベラルや共和党の保守派のイデオロギーも好まない。 彼らは広い意味でのコミュニティに属することを拒み、個人主義者として自分の生活環境をコントロールすることに強い関心を持っている。だから、都市がかつての栄光を取り戻すために税金が使われることに反対する。そういう姿勢は一見保守的に見えるが、もう一方では、都市の貧困や人種の壁を自力で乗り越えてきたマイノリティの人々を受け入れる姿勢も持ち合わせているという。但し、マイノリティの人々がそんなふうに受け入れられたとしても、白人が多数を占めるサバービアでは、どうしてもアイデンティティの危機に直面し、同化を余儀なくされることになるだろう。 ■■都市におけるマイノリティの立場や意識の変化■■ そして、次に取りあげるライ・スアレスの『The Old Neighborhood』を読むと、政治から見放され、危機に瀕している都市のなかにも似たような問題が潜んでいることがわかる。本書も郊外化が進んだこの半世紀を振り返る作品だが、著者のスタンスはまったく違う。彼は、シカゴ、ブルックリン、ワシントンDC、マイアミなどの都市を訪ね、その住人や郊外に転居したかつての住人などにインタビューし、この半世紀のあいだにアメリカが何を失ったのかを検証しようとする。 著者はブルックリン生まれのプエルトリコ系で、シカゴにあるプエルトリコ系のコミュニティで長く生活してきたが、そんな彼自身の体験からは、都市に暮らすマイノリティが置かれた難しい立場が見えてくる。彼が生活するコミュニティの一部の区域では、白人による再開発が進められた。その区域はかつてヤクが取り引きされ、撃ち合いなどがあったが、地元の住民たちが自分たちの手で環境を改善していった。その結果として白人の買い手がついたことは、環境改善の証明となったが、住人たちは高騰した家賃を払えず、立ち退きを余儀なくされる。 |
|
|||||||||||||||