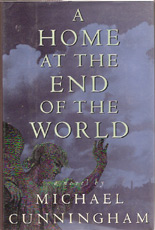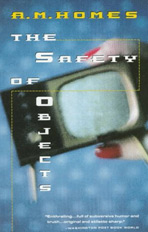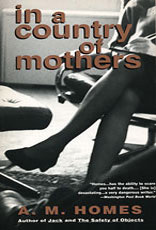90年代のサバービアと家族を対照的な視点から掘り下げる |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| (初出:「SWITCH」1996年8月号、Dr. Fact of Life18、若干の加筆) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
家族を描くアメリカの作家はたくさんいるが、ここではそのなかでも90年代を代表するといえるマイケル・カニンガムとA・M・ホームズの新作に注目してみたい。ふたりの作家の作風にはかなり距離があるが、これまでの作品の内容を対比してみるとなかなか興味深い。 ■■マイケル・カニンガム『A Home at the End of the World』■■ カニンガムのデビュー作は90年の『この世の果ての家(A Home at the End of the World)』だ。この長編は、発表当時は新しいゲイ・フィクションとして注目されたが、その内容には、ゲイという枠を超えた家族そのものに対する深いこだわりを見ることができる。 この作品では、これまでとは違う家族のかたちを模索する三人の男女の姿が描かれている。物語は三部で構成され、クリーブランドの郊外住宅地、大都会ニューヨーク、そしてロックの伝説が息づき、牧歌的な雰囲気が漂うウッドストックというそれぞれの舞台が、主人公たちの模索の重要な背景となる。 ふたりの若者は、一部の郊外住宅地で家族の崩壊を体験すると同時にゲイのアイデンティティに目覚め、二部では、彼らに十才以上年上の女性が加わり、三人は、それぞれに過去を引きずりながらも両親とは違う絆を捜し求める。そして三部では、三人にさらに彼らの赤ん坊が加わり新しい家族のかたちが出来上がっていく。最近では、男女三人の共同生活といった設定はそれほど珍しいものではないが、この小説の繊細な表現や切実さには、心に染みるような奥深さがあった。 ■■A・M・ホームズ『Jack』『The Safety of Objects』■■ 一方、女性作家のホームズも89年のデビュー長編『Jack』にゲイの要素を盛り込み、郊外住宅地に暮らす十代前半の少年ジャックの成長をユーモラスに描いている。ジャックの両親は離婚し、父親が家を出ていく。間もなく父親は自分がゲイで、男と暮らしていることを息子に告白する。 ジャックは、おかまが父親であるはずがないと思い悩み、親友の普通の家庭を羨望の眼差しで見るようになる。ところがある日、彼は、そんな親友の両親のあいだに深い亀裂があることを知り、自分が父親や母親のジャックではなく、ジャックという個人であることに目覚め、成長を遂げる。 ホームズの場合は、このデビュー作と最新作のあいだに短編集と二作目の長編を発表しているが、こちらも個性が際立っている。90年の短編集『The Safety of Objects』は、やはり舞台がすべて郊外住宅地で、周囲の目に怯えつつもドラッグに溺れていく夫婦、妹のバービー人形と倒錯的な恋に落ちてしまう少年、隣人が覗いていることを想像しながら裏庭で自慰に耽る娘、自分が誘拐されたにもかかわらず犯人の男に家を出た父親の姿を重ねてしまう少年、自宅を博物館にして事故で植物人間になった息子を展示している母親などなど、病める郊外が何ともユニークなイメージでとらえられている。 ■■A・M・ホームズ『In a Country of Mothers』■■ 邦訳もある93年の長編二作目『セラピー・デイト(In a Country of Mothers)』では、個人の内面世界というホームズの関心がより鮮明になる。主人公は、マンハッタンに暮らす女性セラピストと彼女の患者になる若い娘のふたりで、彼女たちの心理が絡み合っていく。セラピストには、若い頃に娘を出産してすぐに養女に出さざるを得なかったという過去があり、この患者の話を聞いていくうちに彼女が実の娘ではないという思いにとらわれていく。 先述したように『The Safety of Objects』には、自分が誘拐されたにもかかわらず犯人の男に家を出た父親を重ねてしまう少年を描いた短編が盛り込まれているが、このセラピストと若い娘の関係もそれに近い。また、この物語には、ホームズの個人的な世界が繁栄されてもいる。彼女は実の母親を知らずに育ったという背景があるからだ。 では、そんな設定がなぜ郊外と結びつくのか。それはこの小説では、母親という存在と郊外という空間が意識的に重ねられているからだ。母親は子供を、郊外はそこに暮らす住人を“守る”ものであることが強調され、深く結びついていく。たとえば、このセラピストのクレアが、自分の家族とこの若い娘のために新天地として郊外の家を物色する場面にこんな表現がある。 「クレアは静かな、他と同じに見える家を探していた。個人の要塞。簡単には人を寄せつけない外側。外から見て普通であれば、誰も中を知ろうとしたり気にしたりしない場所。最低、安全には見える場所」 要するに、この物語では、守りたい母親=セラピストと守られたい若い娘の心理が絡み合い、郊外を媒介として妄想が膨らんでいくのだ。 こうしてみると、社会や時代の大きなうねりを背景に既成の家族の変貌を巨視的に描くカニンガムと家族の内面へと深く分け入り、心理を掘り下げるホームズは、非常に対照的な視点と作風の持ち主であることがわかる。そして彼らの新作は、そんな対照がいっそう際立つ作品になっている。 ■■マイケル・カニンガム『Flesh and Blood』■■ カニンガムの新作『Flesh and Blood』には、三世代にわたる家族の営みと変貌が描かれる。しかも中心となる時代が、郊外化の黄金時代=大量消費時代である50年代から現在までに設定され、郊外というアメリカン・ドリームがどう変化してきたのかを一望することができる。 最初の世代は、ギリシャから移民してきたコンスタンティンとイタリア系の妻メアリ。彼らは、長女スーザン、長男ビリー、次女ゾーイの三人の子供に恵まれ、ロングアイランドの郊外住宅地に暮らしている。父親には不遇の時代があったが、住宅の建設会社を経営するギリシャ人に出会ったことから好転し、成功の道を歩みだす。家庭は豊かで平穏に見えたが、家族の結束は着実に失われつつあった。 堅実な長女のスーザンは、父親の理想を受け継ぎ、高校時代に出会った恋人とすぐに結婚し、ニュージャージーの郊外で自分の家庭に欠けていた教養や歴史を育もうと心掛ける。長男のビリーは事あるごとに父親と対立する。父親は、豊かな時代のなかで旧来の価値観が失われ、家庭のなかに脆さがあるのを感じ、それを打ち消すために息子に厳しくあたったからだ。結局ビリーは、大学に進学して家を出るとまったく戻ってこなくなる。次女のゾーイは、自分の世界に閉じこもる子供で、家族から浮き、次第にニューヨークの友だちのところに入り浸るようになる。 |
|
|||||||||||||||||||||||