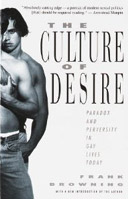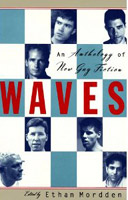ゲイ・フィクションの変遷 |
|||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| (初出:「SWITCH」Vol.12,No5、1994年12月、若干の加筆) | |||||||||||||||
|
ゲイのムーヴメントに大きな転機をもたらした69年のストーンウォール暴動から四半世紀が経過しようとしている。そして最近では、これまでのゲイ・ムーヴメントやゲイ・カルチャーを見直し、これからを展望するような本が目立つように思う。 たとえば、歴史家/活動家であるマーティン・デュバーマンの『Stonewall』では、6人の人物たちの体験を通して、ストーンウォールの時代が再検証されている。フランク・ブラウニングの『The Culture of Desire』では、ゲイが置かれている現在の多様な状況を、それぞれの現場から浮き彫りにしつつ、 ゲイ・カルチャーとは何かという根本的なテーマが問いなおされる。一方、フィクションについては、"Men on Men"のシリーズなど、ゲイの作家たちによるアンソロジーも最近では珍しいものではなくなってきている。新刊のアンソロジー『Waves』では、編者イーサン・モーデンが長文の前書きで、現在に至るゲイ・フィクションの流れを振り返り、 ストーンウォール以降の作家たちを、大きく三つの波に分けるかたちで展望している。 こうした著作からは、エイズの問題、政治的な活動、ライフ・スタイル、セックスを通して得られる宗教的なヴィジョンなど、ゲイをめぐる実に多様な状況が見えてくる。そんななかで、ここで特に注目してみたいのは、ゲイの存在が、硬直しつつあるアメリカン・ファミリーに対して、どのような新しい絆を模索していくのかということである。 それは筆者が拙著『サバービアの憂鬱』で、デイヴィッド・レーヴィットの『愛されるよりもなお深く』やマイケル・カニンガムの『この世の果ての家』などを通して検証したテーマでもある。 『The Culture of Desire』でも、フィクションではなく現実の問題として、このことが重要なテーマのひとつになっている。このテーマを扱う第6章では、まず、家族をめぐるゲイとストレートの深い溝を示す実例が挙げられる。それはたとえば、ゲイであるがゆえに、兄弟から疎外されたり、ユダヤ人としてのアイデンティティを捨て去らなければならなかったり、あるいは、キューバ系のカップルで、 両親には何とか受け入れられたものの、コミュニティのなかで手をつないで歩こうものなら殺されることになるかもしれないというような人々の体験である。 それでは、アメリカン・ファミリーの現状はどうなっているのか。著者のブラウニングは、90年の時点で、70年以降に結婚した夫婦のうち、半分以上が別居か離婚し、子供たちの4分の1近くが片親の生活を送っているという統計を引用し、血縁に基づく家族は、伝統的な意味を確実に失いつつあるという。 著者は、ひとつの例として彼の旧友の告白を引用する。結婚して25年以上になるその友人は、家庭と仕事で深刻な悩みを抱えていた時期があったが、彼には、家族以外にはそれを打ち明けられるような親しい友人がひとりもいなかったという。要するに、核家族化のなかで、仕事や子育てなど両親の負担が大きくなり、気付いたときには彼の人間関係は、同僚と配偶者、子供の三つのカテゴリーに完全に分化し、 友情関係といったものを育む余裕がまったくなくなっていたということだ。これは日本でも同じことだろう。 そこで著者は、ゲイのあいだにある友情関係というものの許容範囲の広さや柔軟さに着目する。簡単に言えば、既成の家族制度のなかでは、男にとって友人=同僚になりがちだが、ゲイの意識では友人=家族に近く、彼らの家族に対する模索からは、ゲイ、ストレートを問わず、新しい関係や役割の糸口が見えてくるのではないかということだ。 これは、新しい家族の絆を模索するゲイ・フィクションの現実的で社会的な背景といっていいだろう。 先ほど、アンソロジー『Waves』の前書きで、編者のイーサン・モーデンが、ゲイ・フィクションの変遷を三つの波に分類していると書いた。具体的には、第一の波は、孤立が強固なアイデンティティに結びつき、自分たちを特異な存在とみなしていたエドマンド・ホワイトやアンドリュー・ホラーランらを指す。これに対して第二の波の作家たちは、自己のアイデンティティを探ると同時に、ゲイをあくまで ”普通” の人々として描く。 そしてこれが第三の波になると、普通と特異の立場が逆転し、ゲイの視点からストレートの世界を異化していくという。 |
|
||||||||||||||