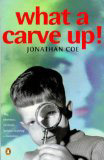イギリスを飲み込む中流化の波 |
|||||||||||||
| |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| (初出:「SWITCH」Vol.13.No.10、1995年12月、加筆) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
サッチャリズムによって急激な変貌を遂げた80年代のイギリス社会では、50年代のアメリカと同じように、消費社会が拡大し、郊外化が進んだ。しかし、誰もが望んで郊外に移っていったわけではない。 イギリスのモダンホラー系の作家クリストファー・ファウラーが95年に発表した『Psychoville』には、中流化の波に飲み込まれるように郊外に移る家族が登場する。物語は、85年と95年の二部で構成され、副題に"a suburban nightmare"とあるように、郊外住宅地を舞台とした悪夢が広がっていく。 85年、14歳の少年である主人公ビリー・マーチは、労働者階級の両親とロンドンの都心部に暮らしているが、再開発の波が押し寄せ、一家はほとんど強制的に真新しい郊外住宅地に転居させられる。その住宅地インヴィクタ・クロスは中流階級の世界であり、一家は排他的なコミュニティのなかで孤立していく。 しかも、一家には知る由もないことだが、彼らの家は、町に持ち上がったゴルフ場開発計画のネックになる場所に位置していた。 そこで一家は、周囲から陰湿な嫌がらせを受けつづけ、母親は自殺し、父子は都会へと帰っていく。しかし、彼らが住み慣れた世界は、ジェントリフィケーションによって一変し、 父親も現実を取り戻すことができないままに命を落としてしまう。そして、それから十年後、このインヴィクタ・クロスに人目を引く若いカップルが現れ、隣人たちが次々と悲惨な死をとげていくことになるのである。 この小説は、物語の組立てや展開という点では、特に後半に進むに従って冗長になり、どんでん返しもいまひとつ切れ味に欠けるという不満は残るが、断片的なディテールがとても印象に残る。 ビリーは、85年のロンドンは、アジア人居住区の焼き討ちやサッカー場での暴動、打ち続く炭鉱ストなどで混沌としていたと回想する。その一部の結びの部分で、インヴィクタ・クロスを追われてロンドンに戻った彼は、テレビでこの町が全国のなかで理想の町に選ばれたことを知る。さらに、翌日の新聞には、 いつかすべての町がインヴィクタ・クロスのようになったらどんなに素晴らしいかという見出しが踊り、政府はテレビを通じて、子供たちのために新しい世界を築く機会が到来したことを訴え、投資を呼びかける。 50年代のアメリカの郊外も、その明るさの影には、冷戦や核の脅威、人種問題などがあったわけだが、この小説からも同じ図式が見えてくる。著者がそんな50年代のアメリカを意識していることは、小説のディテールが物語っている。この小説では、二部でカップルが隣人たちを血祭りに上げていく合間に「アイ・ラブ・ルーシー」のビデオを見ていたり、 ビリーがインヴィクタ・クロスの世界を、ジャック・フィニーの50年代のSF小説「盗まれた街」に重ねてみたりするのである。 そして、『Psychoville』とはジャンルもスタイルもまったく違うが、このような中流化の波を意外な物語のなかで深々と掘り下げているのが、ジョナサン・コーの『What a Carve Up!』である。この小説は、物語があまりにも複雑で説明に困るが、物語の語り手は、小説家のマイケル・オーウェンという人物で、時代背景は、 90年の夏から91年初頭にかけての時期である。彼は、この8年にわたって、イギリスでも名家として知られるウィンショー家の歴史をまとめている。彼にこの仕事を依頼したのは、ウィンショー家の一員で、1906年生まれの老女タビサである。彼には、なぜ彼女がそんなことを頼むのか、その真意がわかっているわけではないが、 この一家の過去の悲劇と関わりがあることは間違いなかった。 |
| ||||||||||||