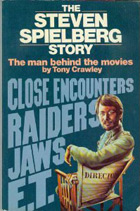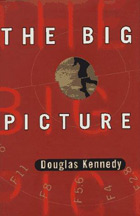サバービアにつづくハイウェイ上の孤独 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| (初出:「SWITCH」Vol.15 No.9 1997年、若干の加筆) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
映画『激突!』はスピルバーグの出世作ということもあり、ご覧になっている方も多いのではないかと思う。平凡なビジネスマンがハイウェイで理由もわからないままに巨大なタンクローリーに追いかけまわされる。そのストーリーはきわめてシンプルだが、この映画には奥深いテーマが埋め込まれている。 この映画の舞台はほとんど路上だが、冒頭の場面では、主人公が運転する車のフロント・ガラスの向うにサバービアの光景が見える。また、主人公と妻の電話のやりとりからは、彼が傲慢な取引先に無理に頭を下げ、妻にも軽蔑されていることがわかる。トニー・クロウリーの伝記『The Steven Spielberg Story』のなかで、スピルバーグはこの主人公について「現代的な郊外生活に埋没した典型的な中流の下のほうにいるアメリカ人」と語っている。 そんな主人公は、タンクローリーに追い回されることによって感情が次々と変化していく。彼は最初、黒煙を撒き散らすタンクローリーに嫌悪感を覚え、対抗心がもたげる。ところが正体不明の相手が本気であることを知ると激しく怯えだす。言葉を変えれば、平穏で安全なサバービアの延長線上を走っているつもりだったものが、突然自分がひとりで、誰にも助けを求められないことを悟るのだ。 そして、さらに興味深いのはその先の展開である。最終的にタンクローリーとの決闘に勝った主人公は一瞬狂喜乱舞するが、しだいに寂しげな姿に変わる。実は郊外生活に埋没していた彼は、恐怖に怯えながらも、必死になって闘うことで喪失した自己を取り戻したような興奮を味わっていたのだ。 ここでは、この映画のようにハイウェイや路上というシチュエーションを通して、郊外生活の歪みを描く小説に注目してみたいと思う。取り上げる3冊の小説には、それぞれにユニークな物語の構造や発想があり、意外なところから郊外生活が見えてくることになる。 まずはスティーヴン・ディクスンが95年に発表した『Interstate』。この小説は、とても長い第1章だけを読むと正攻法の作品のように思えるが、2章、3章と進むうちに作品の狙いが見えてくる。同じ出来事が8章にわたって異なる視点から繰り返し描かれ、章によっては展開が変わっていくのだ。 物語の軸となるのは、ハイウェイで起こったある事件である。ビジネスマンの主人公ナットはふたりの娘たちを乗せてハイウェイを走っていた。その時、ミニヴァンが隣りに並び、助手席の男が窓を開けるようにと合図してくる。何か車の異常を知らせようとしているのかと思ったナットが窓を開けると、男はいきなり銃を向ける。そして発砲し、ミニヴァンは後方に消え去る。その銃弾は、娘のひとりの命を奪ってしまう。 この小説では、この事件をめぐって物語が章ごとに変奏されていくのだが、その流れは実に緻密に計算されている。 まず1章では、事件の顛末が簡潔にまとめられた後、この悲劇が主人公と家族の一生をどのように狂わせていくのかが事細かに描かれる。主人公は犯人を探し求めて1日10時間以上もハイウェイを走りつづける生活を送るようになり、疲れ果てた妻と長女は家を出てしまう。数ヶ月後、彼は犯人たちに遭遇し、彼らを殺してしまう。そして刑務所に送られ、離婚した彼の妻はやがて再婚する。物語は主人公が出所した後もさらに続き、生き残った娘との絆などが描かれ、最終的に彼は孤独な死に至る。 これに対して2章以降では物語が事件の顛末に絞られ、事件の前後の心理や状況が異なる視点で克明に描かれていく。たとえば、主人公は荒っぽい運転をするミニヴァンの男たちを横目で見ながら、あれこれ想像して自分がパラノイアではないかと思ったり、娘が撃たれたことで完全なパニックにおちいった自分を振り返ったりする。あるいは、自分の何が男たちを刺激し、どこで判断を誤ったのかという疑問が強迫観念になっていく。こうしたその場の心理や回想は、第1章にひとつの最悪の結末が提示されているだけに、重々しい緊張感を漂わせる。 そして小説の終盤にはさらに皮肉な展開が待ち受けている。ミニヴァンが並んできたとき、主人公はアメリカ社会の変化について考えだす。郊外化にともなう生活様式や家族の絆の変化、映画や音楽、ゲームが撒き散らす暴力的なイメージが、このミニヴァンの男たちのような人間を生みだし、モラルを低下させ、安心して暮らすこともできない社会を作ってしまったのだと。ところが男たちは発砲もせずに後方に消える。しかし皮肉にも主人公は、前を行くのろのろ運転の車に苛立ち、事故を起こしてしまうのだ。さらに最後の章では、途中の休憩所でミニヴァンの男たちが挑発的な運転をしたことを謝罪し、主人公一家は無事に家に帰り着く。 最後はハッピーエンドというわけだが、もちろん読者がそんな気分になれるはずもない。この小説からは、安全で快適なサバービアの生活に安住している人間の深層に潜む不安や苛立ち、脆さ、強迫観念などが浮かび上がってくるのだ。 スティーヴン・ライトの『Going Native』も、1章だけを読むと正攻法の作品かと思うが、2章以降に予想もしない展開が待ち受けている。物語はシカゴのサバービアに妻と暮らすワイリーが、友人夫妻を招いてバーベキュー・パーティを開くところから始まる。ところが、ショッピング・センターに炭を買いに行ったワイリーは、その直前に起こった発砲事件の犠牲者が運び出されていくのを見て、何かが狂いはじめる。結局彼は、パーティの最中に自分の車も残したまま忽然と姿を消してしまう。 |
|
||||||||||||||||||