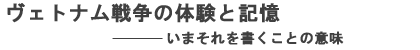 |
||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| (初出:「SWITCH」Vol.14,No.3、1996年4月、若干の加筆) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
1975年にサイゴンが解放され、ヴェトナム戦争(ヴェトナム側からいうと抗米救国戦争)が終結してから、間もなく21年になろうとしている。その間にこの戦争は、ヴェトナム人にとってもアメリカ人にとっても確実に遠い過去のものとなりつつあるはずだが、 小説においては、ヴェトナム戦争という題材はまだ求心力を失ってはいない。 ヴェトナムはドイモイと呼ばれる改革路線によって社会主義経済から市場経済への転換を果たし、経済的には豊かになり、生活も向上した。しかし、そんな時代のなかでこの戦争についての物語を書く作家たちがいる。彼らの作品は、決して単にこの戦争をヴェトナム側から見直そうとしているのではなく、 それぞれにいまこの戦争を題材にすることの意味を考えさせてくれる。 まずはヴェトナムの女性作家ズオン・トゥー・フオンの『Novel without a Name』。彼女は、日本でまったく未知の作家というわけではなく、「流れ星の光――現代ヴェトナム短篇小説集」に短篇が収録されている他、94年には、88年に発表した長編「虚構の楽園」が翻訳出版されている。 この長編は、ヴェトナム人作家の小説のなかで、初めて英訳されてアメリカで出版された作品といわれ、彼女は、すでに国際的にも評価されている。 この『Novel without a Name』に添えられた経歴紹介によれば、彼女は、ヴェトナム戦争の時代、21歳で志願して激戦地におもむき、以後7年にわたってトンネルや地下壕のなかで北の兵士たちと運命をともにした。同じように志願した彼女の同志40人のなかで生き残ったのは3人だけだったという。 そして戦後、彼女は作家として認められていくが、しだいに民主化や人権擁護を声高に訴えるようになり、91年には当局に逮捕され、"国家機密"にかかわる文書を国外に送ったという誣告によって、裁判も開かれることなく7ヵ月間拘留され、現在も執筆ができない状況にある。そして実は、海外に送った文書というのは、 彼女の著作原稿で、そのなかに含まれていたのが、この『Novel without a Name』なのだ。 この小説の主人公は、18歳のときに共産党が掲げる祖国解放の理想に共鳴して人民軍に入り、以来10年間を前線で戦いつづけてきた兵士クアン。彼は、幼なじみが戦場で精神に異常をきたし、後方で拘留されていることを知り、親友でもある上官の協力で前線を離れ、 その幼なじみと故郷の村、過去に向かって旅立つ。その旅からは戦場の様々なドラマが浮かび上がってくる。 たったひとりでくる日もくる日も兵士の遺体を集め、葬ることに追われる女性志願兵は、主人公との一夜に慰めを求めるが、故郷に想いつづける娘がいる彼は、心を苛まれながらも米軍の化学兵器で不能になってしまったという芝居をうつ。補給部隊を指揮する友人と合流した彼は、 部隊が任務の合間に後方に送る棺桶を作っていることを知る。しかも彼らは、安全のためにその棺桶のなかで夜を過ごし、主人公は悪夢にうなされる。著者は、そんなふうにあるときは詩的に、あるときは生々しく戦場を描きだしていく。 そういう意味では、これは北の視点で戦争を見直す作品ともいえるが、決してそれだけの物語ではない。たとえば、主人公は、共産党のインテリのエリート幹部が、列車のなかで、現実と遊離したイデオロギーを振りかざし、大衆を見下しているのを目の当たりにする。 また、彼が想いつづけた娘が、村を仕切る党幹部の慰み物にされ、子供を身ごもっていることを知る。そうした出来事のなかで、主人公の理想は揺らいでいく。そして、必ずしも戦後に変わったとはいえないインテリ主導の党の体質や形骸化したイデオロギーが残したもののことを考えるならば、 この小説は、現代のヴェトナムに理想とは何かを厳しく問いかける作品ともなるのである。 それから、筆者がこの二年くらいのあいだに読んだ小説のなかで最も鮮烈な印象を残し、深い感銘を受けたのが、バオ・ニンの『The Sorrow of War(邦題:戦争の悲しみ/愛は戦いの彼方へ)』だ。著者は、52年ハノイ生まれで、やはり激戦地で戦った経験を背負っている。 69年に彼と同じ部隊で戦地に向かった500人のなかで、生き残ったのはたったの10人だという。この小説はそんな彼の処女長編であり、英訳が94年に出版されて絶賛を浴び、版を重ねている。題名を直訳すると?戦争の悲しみ?となるこの小説は、一見すると戦争の悲劇をリアリズムで描く作品のように思われそうだが、 実際にはまったく異質な物語で、読者を引き込む奥深い魅力を持っている。 |
| |||||||||||||