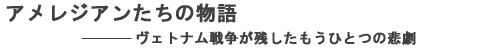 |
||||||||||
| ||||||||||
|
|
||||||||||
| (���o�F�uSWITCH�vVol.14.No.6�A1996�N�V���A��̉��M) | ||||||||||
|
||||||||||
|
�@���{�ł͒Z�ҏW�u�ӂ����ȎR����̍���v�Œm���郍�o�[�g�E�I�[�����E�o�g���[�́A���F�g�i���푈���ނɂ���������������Ƃ̂Ȃ��ňٍʂ�����Ă���B �@���Ƃ��A81�N�̏�����wThe Alleys of Eden�x�ł́A�ח��O��̃T�C�S���ƃV�J�S�Ƃ����ӂ��̐��E��ɁA�E�����N���t�ƃ��F�g�i���l���w�������J���`�����B�A�����J�l�̍Ȃƕʂ�A�����ƂT�N�߂���炵�T�C�S����������N���t�́A���肬��܂ŃT�C�S���Ɖ^�����Ƃ��ɂ��悤�ƍl���邪�A ��g�ق��ї��Ō�̃w���Ƀ�����A��Ă����荞�݁A�A�����J�Ɍ������B�����āA�E�����̐��̂��B���ʂ��A�ʂ̐l���ƂȂ��ăV�J�S�ߍx�Ń����Ƃ̕�炵���n�߂�B �@89�N�̂U��ځwThe Deuce�x�ł́A�ĕ��ƃ��F�g�i���l���w�̂������ɐ��܂ꂽ�A�����W�A���iAmerasian�j�̎�҃g�j�[����l���ɂȂ�B�T�C�S���ɐ��܂������ނ́A �U�̎��ɕ��e�Ɉ�������A�����J�ɓn��B�������A�����J�̐����╃�e�ɓ���ނ��Ƃ��ł����A16�ʼnƂ��т����A���w��N�̔��l�����ނ낷��j���[���[�N�̃X�g���[�g�̐��E�ɓ��ݍ���ł����B �@�Ƃ����悤�Ƀo�g���[�́A�A�����J�ɓn�������F�g�i���l������A�����W�A���Ƃ����ٖM�l�̑��݂�ʂ��āA���̐������߂�B�������ނ́A���F�g�i���̕��y����K���A���t�⊴��A���邢�́A�����l�ɑ��閯���I�Ȉӎ��Ȃǂ܂ŗ������A���A���ȃ��F�g�i���l�̎��_�荞�݂Ȃ���A�ӂ��̐��E�̋��E��˂��l�߂Ă����̂ł���B �@�g�}�X�E�`�E�x�C�X�́wVietnamerica�x��ǂނƁA���������o�g���[�̎��_���A�P�ɇ����F�g�i�����̇��Ƃ��Ĉٍʂ�����Ă��邾���łȂ��A�����I�Ȑ��E�̂Ȃ��Ŕ��ɏd�v�Ȃ��̂ɂȂ���邱�Ƃ��悭�킩��B���̖{�́A���F�g�i���푈���Ɏ�ɕĕ��ƃ��F�g�i���l�����̊Ԃɐ��܂ꂽ�A�����W�A���Ɣނ�̉Ƒ��̑̌���ǂ��m���t�B�N�V�����Ȃ̂��B���̓��e�́A���F�g�i���̃A�����W�A�������������N���ɂ킽���Ă����Ɍ������ɒu����Ă����̂�����Ă���B �@�A�����W�A���̖��́A�푈���������Ă������A�A�����J���{�͉����̓I�ȑ���u���悤�Ƃ͂��Ȃ������B�������샔�F�g�i�����{�́A�A�����J����̎����������m�ۂ���l���Ƃ��邽�߂ɁA���������q�������̏o����W���Ă����B����䂦�ɁA�T�C�S���ח���A�ނ�͂قƂ�ǂ����F�g�i���Ɏ��c����邱�ƂɂȂ����B���̐��́A ���m�Ȑ����͒N�ɂ��킩��Ȃ����A�Q���Ƃ��R���Ƃ�������B���̌�A�����J�́A���F�g�i���̃J���{�W�A�N�U�����������Ɍo�ϐ��ّ[�u��ł������A�A�����W�A���ɂ��Ă̓��F�g�i���l�Ƃ݂Ȃ��A���u����B���̃A�����W�A�������́A���F�g�i���̂Ȃ���"�Љ�̋�"�ƌĂ�a�O����Â���B �@���ǁA���̖��ɂ��ăA�����J�ƃ��F�g�i�������ڌ����n�߂��̂́A���11�N���o�߂���86�N�̂��ƂŁA�A�����W�A���Ƃ��̋ߐe�҂͂��ׂăA�����J�ɓn�邱�Ƃ��ł���Ƃ���ODP�i���@�o���v��j�����ۂɓ����������̂�87�N���̂��Ƃ������B���҂̃x�C�X�́A�z�[�`�~���s�ƃj���[���[�N�ɂ���A�����W�A���̓�Z���^�[�𒆐S�Ɏ�ނ�i�߁A �{���ɂ́AODP���琶�܂�邱�ƂɂȂ������X�̕��ꂪ���߂��Ă���̂����A���̕���͕K��������]�ɖ������ӂ�Ă���Ƃ͌����������B |
| |||||||||