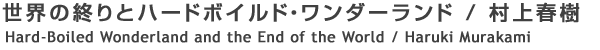 |
||||
|
||||
|
|
||||
| (初出:「SFマガジン」2004年6月号) | ||||
| |
||||
|
『風の歌を聴け』の主人公「僕」は、ロバート・E・ハワードを連想させる架空の作家デレク・ハートフィールドから文章について多くを学んだ。『羊をめぐる冒険』の「僕」は、「カラマーゾフの兄弟」と「静かなドン」を3回ずつ読んだことがあり、冒険の最中には「シャーロック・ホームズの事件簿」を読みつづけている。 『ダンス・ダンス・ダンス』の「僕」は、こんな本の読み方をする。「フォークナーとフィリップ・K・ディックの小説は神経がある種のくたびれかたをしているときに読むと、とても上手く理解できる。僕はそういう時期がくるとかならずどちらかの小説を読むことにしている」。また、こうした村上作品を読めば、彼がレイモンド・チャンドラーやカート・ヴォネガットなどから少なからぬ影響を受けていることがわかる。 村上春樹のなかでは、パルプ小説や文豪の大作、純文学とミステリやSFなどの間に一般的な境界はなく、独自の感覚でごく自然に結びついている。 『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』は、彼のそんな独自の感覚が、小説のスタイルやイマジネーションに最も自由なかたちで現われた作品だといえる。この小説では、「世界の終り」と「ハードボイルド・ワンダーランド」という一見まったく異質な世界に存在する「僕」と「私」の物語が交互に綴られ、次第に共鳴していく。 「世界の終り」の舞台は、中世を思わせる壁に囲まれた街。そこには、たくさんの一角獣が棲息し、住人たちには心がなく、そのために平穏な生活を送っている。「僕」は、影を切りとられ、<夢読み>となり、図書館に並ぶ一角獣の頭骨から古い夢を読む仕事をする。"世界の終り"である街には出口はなく、「僕」はやがて心を失い、住人の一員となる運命にある。 「ハードボイルド・ワンダーランド」の舞台は、計算士を使って機密データを守ろうとする『組織』と記号士を使ってそれを盗もうとする『工場』というふたつの勢力がせめぎあう高度情報化社会、東京。「私」は計算士のひとりだ。計算士は意識を二重構造にする手術を受け、その意識を使ってデータを変換する。地下空間に隠れて研究を行う謎の博士のデータを処理した「私」は、気づかぬうちに深刻なトラブルに巻き込まれている。 |
| |||