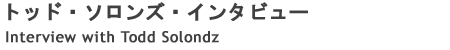 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (初出:「STUDIO VOICE」2005年5月号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【PAGE-2】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
――ボーンアゲイン・クリスチャンというと、ブッシュがその信仰に目覚めることで自堕落な生活から立ち直ったという話も思い出されるのですが、この映画では、その"born-again"という言葉や、先ほどの忠誠の誓いにも出てきた"unborn"という言葉からイメージを膨らませ、ドラマを作っているところがあるように思います。たとえば、家出したアビバが、生まれなかった娘の名前であるヘンリエッタを名乗り、生まれ変わろうとするのは、"unborn"から"born-again"への移行といえると思うのですが。 「その質問は、この映画の核心に触れている。アビバは、子供を生むことで生まれ変わることを望み、実際に別の人間に生まれ変わろうとする。この映画では、アイデアと言葉が遊びの感覚で相互に結びつき、登場人物それぞれの多様で複雑な哀しみや痛みを照らし出していく。生まれ変わることで、過去を消し去ったり、最初から自分を作り直すことができるというのは、極めてアメリカ的な発想で、それは幻想にすぎないのに、とても深く根を下ろしている。僕は、その生まれ変わることをめぐって登場人物たちが苦闘し、自分を受け入れたり、愛を探そうとするところに、なにかとても心を動かされるんだ」 ―一映画の終盤では、アビバの従兄マークが、「自分が変われると思うのは間違いだ。人はずっと同じだ。自由意志はない」と語ります。この映画では、生まれ変わることと変われないことがせめぎ合い、重要なテーマになっているように思えるのですが。 「そう、この映画の中心的なテーマは、"変化"対"静止"なんだ。このマークの台詞は、かなりゆるいメタファーではあるけど、自分では回文的だと思っている。回文には、いろいろな方向に向かうのではなく、常に自分に返ってくるというような性質がある。つまり、合せ鏡のように始まりと終わりでまったく同じ性質を持っている。人間とはそういうものだと思うんだ。マークの無神論的な考え方は、実はかなり僕のそれに近い。僕の場合は彼ほど悲観的で暗くはないけれど、たとえば自由意志に関しては、幻想だと思うし、うぬぼれだとも思っている。人間が変われないということは、もし自分自身の限界や欠陥などを受け入れることができるならば、その人を解放することに繋がると思う。それが、"静止"のよい面なんだ。 ――あなたのこれまでの作品では、サバービアやアメリカ社会に対する独自の切り口や風刺などが、ドラマのなかでいくつかのポイントに集約されていたのに対して、この新作には、そういうポイントがあるのではなく、ドラマの至るところからリアリティが滲み出し、気づいてみるとその世界に深く引き込まれているという印象を受けるのですが、あなたは、これまでの作品と新作では表現に大きな違いがあると思いますか? |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||