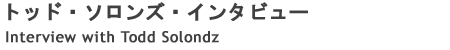 |
||||||
|
||||||
| |
||||||
| (初出:「STUDIO VOICE」2005年5月号) | ||||||
| 【PAGE-01】 | ||||||
 |
||||||
|
自分が生まれ育った場所でもあるニュージャージーのサバービアを舞台に映画を撮りつづけるトッド・ソロンズ。彼の作品の鍵を握るのは常に人間同士の違いだ。登場人物たちは、男女、大人と子供、美醜、階層や貧富、人種、異性愛と同性愛、健常者と障害者、才能や名声などが生み出す境界をめぐって、違いに憧れ、違いに苦しみ、違いを求め、違いを憎悪し、違いに翻弄され、悲惨であると同時に滑稽にも見える状況に陥っていく。 新作の『おわらない物語−アビバの場合−』は、ソロンズの出発点となった『ウェルカム・ドールハウス』のヒロインだったドーンの葬儀から始まる。従姉のドーンがレイプされ、自分の分身が生まれてくることに耐え切れずに自殺したことを知った幼いヒロインのアビバは、自分が彼女と違うことを身を以って証明しようとする。だが、12歳で妊娠にこぎつけたものの、母親から中絶を強要される。それでも諦めきれない彼女は、手術が失敗したことも知らずに冒険の旅に出て、恵まれない子供たちに救いの手を差し延べるクリスチャンのママ・サンシャインに受け入れられる。 この映画では、中絶合法化をめぐって対極にある家族がソロンズ流の皮肉や風刺の対象となるが、ドラマはそれだけでは終わらない。アビバは、年齢、性別、人種、容姿が異なる8人の役者によって演じられる。映画の原題である"Palindromes(回文)"は、アビバ(Aviva)やボブ(Bob)などの名前に現われるだけでなく、台詞やドラマにも埋め込まれている。ソロンズはそんな仕掛けによって、これまでとは異なる視点から人間同士の違いを掘り下げていくのだ。 *** ――ティム・バートンの『シザーハンズ』では、歴史や伝統といった要素が希薄で画一的なサバービアのなかで、孤立する少年の想像力がお伽話的な世界を作り上げます。『おわらない物語』でも、アビバがサバービアからお伽話的な世界に引き込まれていくところが、まず印象に残るのですが。 「僕がサバービアを舞台にした作品を作るのは、まず何よりもそこが、自分という人間を形作った場所だからだ。僕は、ニュージャージーのサバービアで生まれ育ち、早くこんなところを出て、ニューヨークに住みたいと思っていた。いまはニューヨーク在住なので、その夢が現実になったともいえる。『シザーハンズ』は大好きだけど、あの映画の興味深いところは、かつて都会の人々が夢見た、実際には存在しないサバービアを描いているところにあると思う。現代のサバービアは、画一的だとは思わない。白人ばかりでなく様々な人種の人々が暮らし、第二次大戦後ではあるものの、そこには伝統があり、都市にはない文化を生み出している。僕が興味を引かれるのは、空虚や疎外といったクリシェだけでなく、人々がサバービアというフィルターを通してどのように世界を体験し、その人生が形作られていくのかということなんだ」 ――ジョン・ウォーターズ、トッド・ヘインズ、テリー・ツワイゴフ、ケヴィン・スミスなど、サバービアを描く作家にはやはり関心を持っているのでしょうか。 「ひとりを除いてね。ウォーターズはもはやアイコンであって、個々の作品の良し悪しは問題ではない。その存在が作品を越えてしまっている。ヘインズは、ほんとに素晴らしい才能を持った監督で、サバービアだけでなくアメリカの日常を鋭くとらえる文化的なリアリティが際立っている。ツワイゴフは友人でもあるので、私情も入るけど、作品は大好きだし、新作を楽しみにしている。ケヴィン・スミスについては、とてもすてきな人だということで…」 ――『ウェルカム・ドールハウス』のドーンが、いじめっ子からレイプしてやると脅かされても、呼び出しに応じたり、『ハピネス』のヘレンが、自分が空っぽであることに悩み、レイプされれば真に迫った作品が書けると思ったり、アパートの守衛が住人の女性をレイプしたり、『ストーリーテリング』の女子大生と黒人教授の関係とか、この新作で語られるドーンの死の真相やアビバと運転手のボブとの妊娠に繋がらない関係など、あなたの作品には、レイプに絡む表現や言及が目立ちますが、そこにはどんな狙いがあるのでしょうか? 「うーん、そんなに準備してくることないのに(苦笑)。まずこれは重要なことだと思うので指摘しておくと、新作のアビバとボブの関係については、むしろアビバの方が子供を欲しくて彼を襲う、彼は獲物であって、結果的に罪悪感に苛まれるという図式を意識していたんだ。そうでなければ、少女と大人がセックスするシーンは撮れなかったと思う。レイプという要素が作品によく出てくることについては、正直なところ自分ではよくわからない。脚本を書いているときには、クリエイティヴな想像があるだけで、最初から意識して盛り込んでいるのではない。ただひとついえるのは、脚本でセックスを扱うことによって、キャラクターに対する理解が深まり、人間の本質が浮かび上がってくるような面白さがあるということだ。でも日常では、そういうことに対するオブセッションがあるわけではない。たとえば、『ハピネス』のヘレンが、レイプされていればって思うのは、ひとつの風刺だといえる。確かにそうやってよく出てくるということは、何かあるんだろうけど」 |
|
|||||