その男、凶暴につき |
||
| ||
|
|
||
|
【PAGE-2】 |
||
|
このガサ入れにおけるアクションは、男の部屋のなかでの格闘で始まり、我妻が車で男を轢くことによって終わる。 本来ならばこの起点と終点の場面は、緊迫した演出をしたくなるところであるが、起点では刑事たちが折り重なって倒され、我妻もそれを見て笑っているようにユーモラスなものに変えられ、 終点でも我妻が男を二度轢くという笑いを誘う演出がほどこされている。野球のバットが凶器に変わる瞬間というのは、その中間に置かれ、スローモーションも交えて生々しく描きだされる。 北野監督は、人の先入観から緊迫するであろうと思われる場面を肩透かしを食わすような笑いでかわし、その狭間に平凡な日常に潜む凄まじい暴力性を浮き彫りにしてしまうのである。 ちなみに、このバット一本のなかに潜む暴力性は、二作目の『3−4×10月』にも垣間見ることができる。この映画の前半部分には、まったく冴えない主人公雅樹が奮起して素振りを始める場面がある。 キャメラはその素振りを執拗にとらえるのだが、この素振りには不気味な怖さがある。この主人公は、三塁コーチになってもモノのようにただ立っているだけで、球拾いをするくらいしか役に立たない。 彼は野球のルールというものを把握していない。その場の約束事を踏まえていないそんな人間が、ただ黙々と素振りする姿というのは、じっと見つめているだけで異様な空気が漂ってくる。 ルールがなければ、バットはただの凶器以外のなにものでもないのだ。『その男、凶暴につき』のバットは、そんな眼差しの起点として留意しておくべきだろう。 |
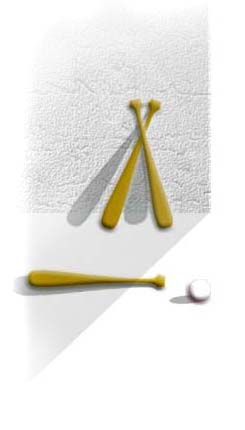 |
|