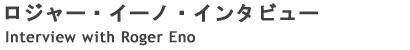|
――あなたは精神障害者のための病院で音楽療法をしていたということですが、どういう仕事をするきっかけは。
RE それまでは、いろいろ勉強になるんで街頭やクラブで演奏していたんだけど、偶然、そういう仕事の話がきたんだ。
それで、自分の音楽を生かせるんじゃないかと興味を持って、2年半くらいやっていた」
――あなたの音楽は、意識とか精神を共鳴させるような魅力がありますが、そうした仕事の影響はありますか。
RE その仕事をする前からもう自分のスタイルはできあがっていたけど、仕事のおかげで、
音楽がとても深く人に影響を及ぼすということはよくわかった。たとえば、話すことができない重度の障害者でも、
音楽によって気持ちを動かすことができる。特に、弦楽器は効果が大きいんだ。ゆっくりとした弦楽器による音楽は、
騒々しい音楽とは違った意味で、より大きな効果をもたらすように思える。音楽の内容にもよるけど、エレクトロニクスを使った音楽が、
ネガティブな効果をもたらすこともわかった。直接的な影響はないけど、音楽の微妙な力がいかに重要であるかということはよく理解できたよ。
――具体的にはどんな仕事をしていたんですか。
RE たとえば、自閉症の子供をグループに参加させようとしたり、逆に騒がしくて精神が散漫になっている子供を集中させるときなどは、
小さな音でドラムを叩くことによって効果が出てくるんだ。それから、肉体的なレベルでは、筋肉が硬直してしまって車椅子に座っている障害者に対して、
肉体を治すという考え方ではなく、まず音楽を楽しむということから入っていく。もっと年をとった障害者の場合には、音楽の話をして、
音楽と結びついた記憶を呼び覚ますことからいろいろな効果が出てくる。要するにグループ療法の一種なんだ。
――音楽療法をする前にできあがっていたというあなたのスタイルのベースになっているのは何ですか。
RE 子供の頃はブラス・バンドで演奏していて、その音楽は、メロディもハーモニーもとてもシンプルで、
そうした構造というものが一番の基礎になっていると思う。その後というのは、
構造というよりも自分のフィーリングにしたがって音楽のフィールドを広げていった。現代の作曲家は音楽をどんどん複雑にしているけど、
ぼくは逆に、シンプルなメロディの抽象性を広げようとしてきたんだ。
――ステージでフィリップ・グラスとかペンギン・カフェの話もしてましたが、彼らの音楽については。
RE あんまりはっきり言うと、後ろから刺されそうだから(笑)。音楽を単純化していく発想には共鳴できるけど、
彼らはそれに過剰なエモーションを上乗せしている。単純化はとても重要なことだけど、ぼくは、それを感情的な音楽にはしたくないんだ。
ミニマリストの作曲家のなかでは、アメリカのジョン・アダムズが最高だ。彼は、ミニマリストのフォルムを基調として、とてもカラフルで表情豊かな音楽を作っている。
――ステージで演奏したあの第一ヴァイオリンがグラス風のメロディを反復する曲は、ユーモアというかパロディかと思ったのですが。
RE (笑)その通りだよ。最初と終わりがペンギン・カフェ風のサウンドで、その真ん中にグラス風のサウンドが挟まっているんだ。タイトルは<グラス・アンド・カフェ>というんだ(ここで一同大爆笑する)。
――クラシックを勉強していたわけですが、反発を感じたりしませんでしたか。
RE 正確にいえば、ぼくが勉強したのは作曲ではなく、和声についてで、この違いは大きい。和声を勉強するというのは、言葉を勉強するようなもので、ぼくの言葉というのは滅茶苦茶だったから(笑)。
つまり、文法を勉強して、言葉から違った意味を引き出すのと同じことを音楽の構造に対してやるようなものなんだ。あの頃いちばん面白かったのは、音楽史だった。
音楽がどのように発展してきたのかということは、とても重要なことだ。かつて音楽には様々な区分があったんだ。教会の音楽があれば、戦争のための音楽や食事の音楽、いまはそういうことがみんな忘れられて、
エンターテインメントということで括られてしまっているけど、それぞれの音楽が持っていた社会的な意味というのはとても興味深いし、ぼくには役立っている。
ぼくの音楽がどんなふうに使われているかということについては、様々な答が返ってくる。アメリカに住むある女性は子供を産むときに聴いていたということだし、
別のアメリカ人の医師は、自分の病院にぼくの音楽を流しているというし、またある人は、勉強するときにリラックスするために聴いている。
――今度、日本でリリースされる88年のセカンド・アルバム『Between Tides』は、弦や管楽器のアコースティックな響きがかなり厳選され、ピアノと調和していると思うのですが。
RE ファースト・アルバムは、実験的な作品ではなく、ぼくのピアノを中心にしたとても自然なピアノ・アルバムだった。それに、エレクトロニクスの要素を加えてあるのは興味深いところだけど。
それに対してセカンドでは、エレクトロニクスの響きよりも自分が気に入っているアコースティック楽器を多く使い、それを、色彩を豊にするような効果音として使っているんだ」
――現在、3枚目のアルバムを製作中ということですが、どんな内容になっているのですか。
RE (オーパル・イヴニングの)ステージで演奏した曲が何曲か入るよ。それから、素晴らしい女性シンガーの歌を入れる予定で、ぼくがその詞を書いている。後は、マテリアルはいっぱいあるんだけど、
まだ始めたばかりではっきりとは言えないんだ。アルバムはリスナーがずっと聴きつづけるものだから、レコーディングで間違いをおかせば、それをずっと後悔することになるから、とても気を使うんだ。
コンサートでは、もっと瞬間的なインパクトがあるから、冒険することもできるけどね。
――ステージでマグリットの絵の話などもしてましたが、絵にインスパイアされて曲を作ることもあるのですか。
RE そう。あの曲の場合は、マグリットの画集をピアノのうえに置いて、その絵から感じる雰囲気をもとに即興でピアノを弾き、それを録音しておいて、曲にしたんだ。
こういう作り方はぼくの習慣のようなものなんだ。そうした即興のなかには素晴らしいアイデアが潜んでいて、それを曲にしていく。そういうやり方で、自分の精神がいつもクリシェに陥らないようにしているんだ。 |