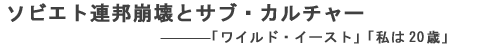 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (���o�F�uSWITCH�vVol.13,No.4�A1995�N�T���A���M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�����y���X�g���C�J�Ȍ�̃��[�X�E�J���`���[���� �@�y���X�g���C�J�Ȍ�𒆐S�ɁA���V�A�̃��[�X�E�J���`���[�͂����q�����[�E�s���L���g���́wRussia's Youth and Its Culture�x(94)�Ƃ����{������B���҂̓��V�A�E�����̐����A�Љ�w����ɂ���o�[�~���K����w�̍u�t�Ƃ������ƂŁA���e�͏��������Ƃ�������邪�A��͂苻���[���B�S�̂̍\���͎O������Ȃ�A�ꕔ�ł͗��j����̊ϓ_����A �����Ɠ����̃��[�X�E�J���`���[�̈Ⴂ�����炩�ɂ���A�ł͐V���A�G���A�������Ȃǂ����ƂɁA��l�̎��_���猩���Ă����҂��߂���̕ω��������A�O���ł́A���Ҏ��g�̃t�B�[���h�E���[�N�Ɋ�Â���҂̌�������������ɂ���Ă���B �@���҂�88�N����89�N�A������91�N�Ƀ��X�N���ɑ؍݂��A��҂����̗l�X�ȃO���[�v�ƌ𗬂������A�����W�߁A��������̎O���ɂ܂Ƃ߂��B�����ɂ́A��҂����̃O���[�v�ނ����n�}�����荞�܂�Ă���B���̌n�}�́A�p���N�A�w���B���^�A�q�b�s�[�A�o�C�J�[�A�X�P�{�[�A�u���C�N�E�_���X����A ������v�z�Ɏx�������߂�l�I�i�`��X�L���w�b�h�Ƃ������t�@�V�X�g�A���邢�͋����D��̔��t��u���b�N�E�}�[�P�b�g�A����Ƀ{�f�B�r����J���ҊK�����\���郊���[�x���B�ȂǁA�ŏI�I��30�قǂ̃O���[�v�Ɏ}�����ꂵ�Ă���B����̓y���X�g���C�J�Ƃ������m�̑̌���������҂������A���ꂼ��ɋ��߂�A�C�f���e�B�e�B�̕��ނƂ�������B �@�ꌩ����ƃ��[�X�E�J���`���[�͐���オ��������Ă��邩�̂悤�����A���҂ɂ�����́A�������肵���A�C�f���e�B�e�B�ł͂Ȃ��Ƃ����B���Ƃ��A�����[�x���B�͍x�O���烂�X�N���ɉ��������A���������ǂ��Ղ�̃p���N��w���B���^�E�L�b�Y���P�����A���咣���Ă��邪�A������Ƃ����Ė��m�Ȉ����S�Ƃ��J���ҊK���̈ӎ�������킯�ł͂Ȃ��B ����������Ƃ��Ď��������E���d��悤�Ȏh�������߂Ă���ɉ߂��Ȃ��B����A���҂��C���^�r���[��������p���N�E�L�b�Y�̊y���݂́A�钆�ɍ�蕨�̃}�V���K���������ăr���̉����n��������ƂŁA�ǂ���炻��Ȃӂ��ɂ��ēs��̃W�����O�����x�z���Ă���C���ɂЂ����Ă���悤���Ƃ����B �����Ō�̃\�r�G�g�f��w���C���h�E�C�[�X�g�x���� �@�J�U�t�X�^���o�g�̃��V�h�E�k�O�}�m�t���ē����w���C���h�E�C�[�X�g�x(93)�ɂ́A�s���L���g���̂��̖{���畂���яオ�鐢�E�Ƃ̌q�����������B���Ō�̃\�r�G�g�f�懁�Ƃ������肪�t����ꂽ���̍�i�́A���V���́w���l�̎��x���x�[�X�ɁA�n���E�b�h�f���}�J���j�E�E�G�X�^���̃p���f�B�A�p���N�E���b�N��{�[�_�[���X�ȃt�@�b�V�����ȂǁA �l�X�ȗv�f�����荞�܂�Ă���B�_���ɂ���鑾�z�̎q�������Ƃ������l�̈�c�ƃo�C�J�[�̑Η��Ȃǂɂ́A�����̎�҂����̑Η��\�������b�������悤�Ȗʔ���������B �@�������ł���ۓI�Ȃ̂́A�l�X�ȗv�f�����荞�܂�Ă���ɂ�������炸�A�ǂ��ɂ��˂���������̂��Ȃ��Ƃ������Ƃ��B���̉f��͖{���I�ɂ́w���l�̎��x���������ǂ����ɓ��ݏo���Ȃ��B���ꂪ���Ƃ��s�v�c�Ȉ�ۂ��c���̂ł���B �@�ē̃k�O�}�m�t�́A���̉f��ɂ��Ă���Ȃ��Ƃ�����Ă���B�u�T�u�E�J���`���[�́A�嗬�����Ȃ����Ă͐��܂�Ȃ����������������̂ł��B���̍�i�́A���̃T�u�E�J���`���[�f���Ă��܂��B�\�A�̎嗬���������������̐�A�嗬�������l�A�T�u�E�J���`���[�����݂��܂���B�����炱�̉f�悪"���X�g�E�\�r�G�g�E���[���B�["�Ȃ̂ł��v�B �@���̃R�����g�ŕM�҂��v���o���̂́A��q�����wRussia's Youth and Its Culture�x�̓ŁA���҂������Ă��邱�Ƃ��B�}��R���\���[���́A�y���X�g���C�J�Ȍ�ɕ\����ɑ��X�Ɠo�ꂵ�Ă����҂����̑Ή��ɋꗶ����B���Ƃ��Δނ�́A�p���N�A�w���B���^�̃t�@����q�b�s�[�A�o�C�J�[�������A�܂Ƃ��ȘH���ɓ������߂ɁA��p�̃N���u��ݒu���A�o���h�̊����Ȃǂ܂Ŏ菕������B ����́A�ƍ߂ɑ���Ȃ���A���I�@�ւ����ł����͂��邱�Ƃ��Ӗ�����B �@�����Ȃ�Ɗm���ɁA�T�u�E�J���`���[�͈Ӗ����������ƂɂȂ�B�����āA�k�O�}�m�t���f�����{�g���ăT�u�E�J���`���[������̂��A�O�����ȃ��b�Z�[�W�̂悤�Ɏv���Ă���̂ł���B���邢�͂���́A�w�[���V�e�B�x�ɏo�Ă��邠�̔����ق̃T�u�E�J���`���[�łƂ�������B�w���l�̎��x�Ƃ������ꕨ�ɁA�Ӗ����������T�u�E�J���`���[�̎c�[�����ׂĕ��荞�݁A�ߋ��ւƑ��苎��Ƃ������Ƃ��B �����u����20�v�ƃX�e�B�����[�M���� �@�����Ă����ł�����{���ڂ��Ă݂����̂��A�}�������E�t�c�B�G�t�ḗw����20�x���B���̉f��͈ꌩ�����Ƃ���A����܂ł̗���Ƃ͂܂������W�Ȃ��悤�Ɍ�����B�w����20�x��62�N�ɐ��삳�ꂽ�\�r�G�g�f��ŁA�����I�Ȉ��͂ɂ���đ啝�ȏC����]�V�Ȃ�����A���J��65�N�܂ʼn������ꂽ��i�ł��邩�炾�B���Ȃ݂ɍ�����J�����̂́A�ē��炪�����������S�łł���B |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||