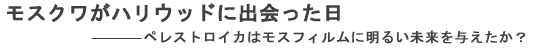 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (初出:日本版「Esquire」1991年7月号、若干の加筆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
昨年(1990年)の12月、モスクワでは、『バック・イン・ザ・U.S.S.R.』の撮影が終盤にさしかかっていた。この映画は、製作総指揮にあたっているルイス・A・ストローラーの言葉を借りれば、"全編モスクワ・ロケによる初のアメリカ映画"ということになる。 物語は、大学の休暇を利用してモスクワにやって来たアメリカ人青年が、謎めいたロシア人の娘レナとふとしたことで知り合い、"アイコン(黒いマドンナ像)"をめぐって暗躍する得体の知れないブラック・マーケットの一味に追われるはめになるといった内容だ。アメリカ人青年には、 『フィールド・オブ・ドリームス』や『7月4日に生まれて』に出演していたフランク・ホェーリー、ロシア人の娘には、ソビエトで人気の女優ナタリア・ネゴーダが扮し、ロマン・ポランスキーがブラック・マーケットの黒幕を演じている。 色鮮やかなモザイクが美術館を思わせるモスクワの地下鉄の構内では、ふたりの男女が、地下鉄の閉まりかけたドアに滑り込み、追手を逃れるシーンが撮影された。現場には、スタッフの間で、英語にまじってロシア語がさかんに飛び交っていた。というのも、この映画は、ハリウッド資本に、 世界最大の規模を持つソビエトの映画スタジオ、モスフィルムが撮影協力するという形で進行していたからだ。 ■■モスフィルムの方向転換■■ ペレストロイカは、ソビエトのあらゆる価値観を変えつつあるが、映画も例外ではない。ソビエト映画界を代表するモスフィルムは、いま、大きな転換期にさしかかっている。 モスフィルムは、ロシア革命の7年後の1924年に設立された。モスクワのレーニンヒルス区に位置し、スタジオの規模は125エーカー(約51平方km)で、4500人あまりの従業員を抱えている。年間45〜50本の劇映画を製作し、約12本のTVシリーズ番組を製作している。最近の製作予算は、年間1億5千万ドルといったところだ。 そのモスフィルムに、明らかな変化があったのは一昨年のこと。モスフィルムは、今までの古い体制の改革に乗り出し、州に対する全面的な補助金依存をやめ、独立採算の道へと踏み出した。かつてモスフィルムで働き、いまは、ハリウッド側から『バック・イン・ザ・U.S.S.R』のプロデュースにあたっているイルマー・タスカが、 これまでの20年間、モスフィルムのシステムはまったく変わることがなかったと語っていたことを考えると、これは大きな変化に違いない。 そこでモスフィルムは、ワールド・ワイドな市場でヒットする作品の製作に目を向け始めた。その第一歩として、モスフィルムは、ロケ地がソビエトの作品で、共同製作可能な外国の映画会社にアプローチをかけ、ジョイント・ベンチャーに乗り出した。モスフィルムのジェネラル・ディレクターであるウラディミール・ドスタルは昨年、 「今年45本の作品がモスフィルムで作られ、うち20本がジョイント・ベンチャーである」と語った。 具体的には、イザベラ・ロッセリーニ、トム・コンティ主演で、イタリアとの合作『The Siege of Venice』、『バック・イン・ザ・U.S.S.R.』、そして、オレーグ・ヤンコフスキーとマルコム・マクドウェル主演で、ロシア人のカレン・シャフナザーロフが監督にあたった、イギリスとの初の合作となる『The Assassins of the Tsar』といった作品の製作が、昨年から今年にかけてモスフィルムで進められた。 しかし、実際に訪れたモスフィルムから、そんな急激な変化を感じとることはなかなか難しい。煉瓦作りの建物や大理石を張った広間の空間などは、重々しく、ひどく古びている。通路にあるドリンクの自動販売機などは完全なアンティックだ。そして、最も印象に残るのが、モスフィルムで製作された古い映画のポスターが壁を埋める一角だ。 なかでも、セルゲイ・ユトケーヴィッチ監督の『パリのレーニン』や『ポーランドのレーニン』、ミハイル・ロンム監督の『一九一八年のレーニン』といった一連のレーニン作品のポスターが目につく。この時間が淀んでいるような、老朽化した巨大なスタジオを立て直すのは容易なことではないだろう。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||