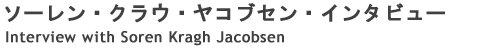 |
||||
|
||||
|
|
||||
| (初出:「MIFUNE」劇場用パンフレット、若干の加筆) | ||||
|
|
||||
|
ソーレン・クラウ・ヤコブセン監督の「MIFUNE」は、ラース・フォン・トリアー(「奇跡の海」)を中心としたデンマークの四人の監督集団〝ドグマ95〟が始めた試みの#3にあたる。ドグマ作品では、映画製作に厳しい制約が課される。その記念すべき#1であるトマス・ヴィンターベアの「セレブレーション」には、 ドグマのひとつのかたちを象徴するような独特の緊張感があった。ところがこの「MIFUNE」は、対照的にドグマをほとんど意識させない作りになっている。それはヤコブセン監督の一貫した主題がこの作品にきわめて自然なかたちで現れているからだ。 ――「エマ」「マイ・リトル・ガーデン」、そしてこの「MIFUNE」を観ると、あなたの映画では、子供の世界や視点が作品のなかで重要な位置を占めていますが、その出発点はどこにあるのでしょうか。 ソーレン・クラウ・ヤコブセン(以下SKJ)監督になる前に、デンマーク放送で児童番組の制作に関わり、子供たちと接する機会を持ったということもあります。しかしわたしにとって子供の世界が重要な理由は他にあります。デンマークは決して人口が多くないので、プロの役者の数も限られます。 そのためいつも同じ俳優を起用しなければならなくなるのです。そこでどうしたら新しい顔や才能を発掘できるだろうと考えたときに、子供たちに行き着きました。たとえば「エマ」では、5千人の少女と話をして主役を決めたというように、自分が求める顔やキャラクターを自由に選ぶことができるのです。 経験がない子供をいかに演出するかということにも非常に魅力を感じます。さらに子供の視点というのは、未来への視点でもありますからね。 ――ドグマの話がきたとき、このアイデアについてどのような印象を持ちましたか。 SKJ この話がくる前にわたしは、「マイ・リトル・ガーデン」を撮ったのですが、この映画は4カ国の共同制作で、プロデューサーなど様々な人々がわたしの仕事に口を出してきました。そんなわけで、わたしが自分の作品を完全にコントロールすることを渇望しているときに、ラースから話がきたのです。 わたしは映画を作るときに、別のものをメタファーとして思い描くことがよくあるのですが、ドグマについては、MTVアンプラグドを連想しました。わたしは最初にアンプラグドのことを知ったときに、たとえばE・クラプトンのように才能があって、 最新のテクノロジーを使ってどんな音でも作れるミュージシャンが、なぜわざわざ原点に戻るようなことをするのか不思議でした。しかし、何でもできるからこそ、本当に何ができるかを確認したい、自分を試したいのだという結論に至りました。そしてドグマにもそれと共通する意味があると思いました。 |
| |||