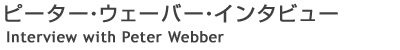|
||||
|
|
||||
| (初出:『ハンニバル・ライジング』劇場用パンフレット) | ||||
|
ハンニバル・レクター誕生の謎が解き明かされる『ハンニバル・ライジング』の監督に起用されたのは、『真珠の耳飾りの少女』で注目を浴びたイギリス出身の新鋭ピーター・ウェーバーだった。彼は、これまでのハンニバル・シリーズと『ハンニバル・ライジング』の違いをこのように語る。 「もちろん主人公となるのはハンニバル・レクターですが、これまでの作品が、サイコスリラーやFBIの捜査ものというかたちをとっていたのに対して、この作品で(脚本も手がけた原作者の)トマス・ハリスは、何かもっと神話的で、大人のお伽話のような世界を生み出していると思います。心理的な要素もこれまでと同じように扱うのではなく、もっと根源的なものに向かっている。だから私はこれを、大人のお伽話、あるいは“ゴシック・リベンジ・ウエスタン”というようにとらえています。この作品には、よりスケールの大きな世界があると思います。また、これまでの作品が非常にアメリカ的だったのに対して、この作品はヨーロッパ的です。つまり私たちは、これまでの作品でみなさんが馴れ親しんでいる要素を取り去り、まったく違う、新しいものとして再生しようとしたのです」 『ハンニバル・ライジング』の導入部で、レクター家は戦火に巻き込まれ、まだ幼いハンニバルとミーシャは、森に囲まれた山小屋に取り残される。そんな兄妹の姿は、「ヘンゼルとグレーテル」を想起させる。ウェーバーのコメントに出てきた「大人のお伽話」とは、現実のドラマに盛り込まれたそんな物語的な要素を意味しているように思える。 「そう、まったくその通りです。「ヘンゼルとグレーテル」を連想するというのは、鋭い洞察です。というのも、この映画のなかにたびたび出てくる歌ですが、「Ein Mannlein steht im Walde ganz still und stumm,」というあの歌は、「ヘンゼルとグレーテル」のオペラからとられているのです。原作でそれを引用しているトマスは、最初からお伽話的な要素を明確に意識していたのだと思います」 小説と映画では表現の方法が異なるが、ウェーバーは、脚本も手がけたトマス・ハリスとどのように共同作業を進め、映画の方向性を決定していったのだろうか。 「トマスは、ストーリーテリングに関して独自のヴィジョンを持っていましたが、脚本を手がけるのは初めてだったので、彼が映画的なストーリーテリングを理解する手助けをしました。小説と映画では、強調される部分も違いますし、内容も変わってきます。具体的には、ハンニバルの叔父が小説では登場しますが、映画では登場しません。他にも、映画ではいくつかのエピソードを削りました。この映画を私のヴィジョンだというつもりはさらさらありませんが、どんなクルーを使い、どんなセットを選び、どんな照明をあてるかなど、様々な判断を下すのは監督の仕事なので、当然、映画には私の感性が反映されることになります。私が目指したのは、トマスのヴィジョンにできるだけ敬意を払い、観客が楽しめる映画を作るということです」 |
| |||