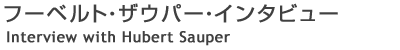|
||||||
|
|
||||||
| (初出:「キネマ旬報」2007年1月上旬号) | ||||||
|
フーベルト・ザウパー監督の『ダーウィンの悪夢』では、アフリカ最大の湖ヴィクトリア湖で大繁殖した外来魚ナイルパーチによって変貌する地域社会を背景に、人々の過酷な生存競争が映し出される。オーストリア出身のザウパーとアフリカの関係は、前作の「Kisangani Dairy」(98)に始まる。 「ルワンダの虐殺を逃れてコンゴに来た難民を取材し、映画を作るつもりだったんです。ところが現地に行ってみると、内戦になってそこから出られなくなり、戦いを目の当たりにすることになった。アフリカへの初めての大旅行は、凄いことになってしまった。その記憶は鮮烈で、いまだにそのことを考えない日はありません。私の人生のなかでその体験がはっきりとした節目になっているのです」 ザウパーの世界観や創作のなかで、アフリカは非常に重要な位置を占めている。 「私にとってはアフリカというのは、他の人々の人生や人間の内面、人類の将来であるとか、あるいはアウシュヴィッツであるとか、それを通していろいろなものを見ることができる透明な窓のようなものなのです。だから私が作っているのは、単にアフリカについての映画ではない。私の仕事は、アフリカを通して、もっと広いものを見せることなのです」 『ダーウィンの悪夢』の舞台は、ほとんどヴィクトリア湖畔の地域に限定されているが、映画からははるかに広い世界が見えてくる。それはたとえば、在来魚を駆逐していくナイルパーチと加工された魚を運ぶ輸送機のイメージから広がっていく世界だ。一説には、ナイルパーチは、60年代にウガンダの漁業を改善するために雇われたイギリス人が放流したといわれる。70年代には、タンザニアとオランダの政府が協力して、トロール船を建造し、湖の生態系や自然の回復力をまったく調査することもなく、一日に60トンのシクリッド(在来魚)を加工できる魚粉工場を建設する計画を立てた。そしていま、シクリッドはナイルパーチに変わり、トロール船は輸送機に変わり、その輸送機は一回に55トンもの魚を現実に運んでいる。加工された魚はヨーロッパや日本に送られ、地元の貧しい人々は、残ったあらを食べて、飢えを凌ぐ。 「いま挙げられた背景はほんとにその通りだと思いますし、ナイルパーチと輸送機は、まさしく南北の格差とグローバリゼーションを象徴していると思います。私がやるべきことは、観客が映画のなかに象徴を見出したり、多様な解釈ができるような鍵を差し出すことです。たとえば、加工工場の場面には、「あなたは巨大なシステムの一部」という言葉(壁のカレンダーの標語)がありますが、あの時点であの場面に出てくるから、その意味が深くなる。(積荷が重すぎて)墜落した輸送機の残骸も、ある位置からは丸い形にしか見えませんが、別の位置から撮れば、魚のあらのように見え、意味を持つことになる。この映画のラッシュは200時間もありました。それを2時間にまとめるには、99%捨てなければならないわけです。だから編集の際には、いろいろな意味を考えながら再構成していきました」 |
| |||||