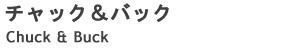 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (初出:『チャック&バック』劇場用パンフレット) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
『チャック&バック』』主人公バックは、子供の時代のまま時間が停止してしまったようなアダルト・チルドレンだ。しかも、かなりの重症というべきだろう。彼は、子供の頃にチャックとやった性的な冒険が脳裏に強く焼き付いている。そのために、10数年ぶりに再会したチャックに、抱擁を逸脱したきわどい仕草を見せてしまう。 それでもまだ最初のうちは、純粋なバックに対するチャックの態度の方がやはり冷たく映る。ところが、バックがロスに引っ越し、チャックと婚約者を執拗につけ回すようになると、さすがに彼がストーカーに見えてくる。映画は、そんなバックが、彼なりの奮闘と挫折を経て、大人の世界に踏みだしていく姿を描いている。 このバックの成長のドラマで最も興味深いのは、現実と虚構に対する視点である。チャックを追いまわすバックは、偶然目にした児童劇場に触発され、自分と彼の過去や現在を童話風にアレンジした戯曲を書き、劇場で上演しようとする。その芝居は、チャックにしてみれば、おそらくは嫌がらせ以外の何ものでもないだろう。しかしバックには、戯曲や演劇が重要な空間となる。 それ以前の彼は、チャックを無理やり子供時代に引き戻そうとしてきた。彼が体現するアダルト・チルドレンやストーカーは、現実に対して完全に閉じた世界に存在しているのだから、それは仕方がない。演劇にしても、彼の目的に変わりがあるわけではない。しかし、子供時代と現在という単純な図式に、演劇というもうひとつの空間が絡みだすことによって、現実と虚構にねじれや転倒、飛躍が生まれ、バックが現実を受け入れていく糸口を作るのである。 この現実と虚構の関係は、ウディ・アレンの映画の世界と対比してみると、その面白さがいっそう明確になるのではないかと思う。アレンは自分の作品のなかで、現実と虚構のせめぎあいを描きつづけてきた。虚構とは、劇中に盛り込まれた小説や演劇、映画の架空の世界であり、複雑な男女関係から生まれる勝手な思い込みなどである。 昔のアレン作品では、登場人物がどんなに虚構に引き込まれても、現実の基盤は決して揺るがず、最後には現実に戻ってきた。ところが『重罪と軽罪』あたりから、虚構が現実を模倣しているのか、現実が虚構を模倣しているのか曖昧になりだし、現実は個人の選択に左右されるものに変わる。そして『ブロードウェイと銃弾』や『地球は女で回ってる』などでは、劇中の演劇や小説が現実を大胆に取り込むばかりか、時に虚構が現実を凌駕してしまうまでになるのだ。 そんなアレン作品の流れを踏まえたうえで、ここでは特に『地球は女で回ってる』に注目してみたい。この映画の現実と虚構の関係には、『チャック&バック』に通じるものがある。主人公である売れっ子の小説家は、現実の世界のなかで周囲から孤立しかけている。というのも彼は、別れた妻たち、愛人、友人、家族のプライバシーをほとんどそのまま滑稽な小説の題材にしているからだ。 映画はそんな主人公の現実の世界と虚構の世界を、別のキャストを使って対置するように描く。彼は現実を食い物にしながら、彼が創造した人物たちとともに、それがまるで現実であるかのように虚構の世界を生きている。つまり、彼は現実逃避していると同時に、彼が逃避した虚構の世界が一人歩きを始め、リアリティにおいて現実を越えてしまうのである。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||