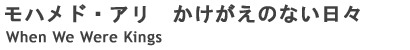 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (初出:『モハメド・アリ かけがえのない日々』劇場用パンフレット、若干の加筆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
モハメド・アリは、単に偉大なボクサーであるばかりでなく、神話的な存在でもある。ザイールの首都キンシャサで行われたアリとフォアマンのタイトルマッチは、そんなアリ神話のひとつの大きなハイライトになっている。それだけに、このタイトルマッチをクライマックスとする世紀のイヴェントが再現されるこのドキュメンタリーには、誰もが心を揺り動かされるに違いない。 リアルタイムでこの出来事を知る人には、あの時の興奮と熱狂が甦り、もっと若い世代の人は新鮮な感動をおぼえることだろう。アリは神話を生み、それに感動した人々がさらにアリ神話を積み上げていく。 しかしながら、このドキュメンタリーを、感動を呼ぶ事実としてだけではなく、映画としてみるとき、筆者はもう少し違うことを感じる。昨年(1996年)アメリカで出版されて話題となり、しばらく前に翻訳もされた『モハメド・アリの道』という本のなかで、著者のデイヴィス・ミラーは、こんなふうに書いている。「世の人々が(僕も含めて)アリとはだれかについて語るのを耳にするたびに、 それが正しかったためしはない。アリにはそれがよくわかっていて、かえってそのことを楽しんでいる」 子供の頃からアリに憧れていたミラーは、アリがパーキンソン症候群に苦しめられるようになった後で彼と出会い、その交流を本書で、ノンフィクション=ノヴェルともいうべきスタイルで綴っている。筆者が来日したミラーにインタビューした時、やはり彼はこんなふうに語っていた。「人々は常にアリという人間をカテゴライズすることを繰り返してきたが、そのたびに彼は期待を裏切ってそこから逸脱してきた。それがアリの最も素晴らしいところだと思う」 『モハメド・アリ かけがえのない日々』には、様々な人々のアリに対する眼差しや思惑が錯綜している。スパイク・リーはアメリカに生きる黒人の立場からアリを見つめ、ジョージ・プリンプトンにはスポーツライターとしての眼差しがある。人間のプリミティヴな本能や衝動に強い関心を持つ一方で、反権力的な姿勢を貫いてきた作家ノーマン・メイラーは、独裁制の恐るべき監獄のうえに建つスタジアムで行われる闘争を象徴的なものと見ている。 プロモーターのドン・キングは、ザイールの独裁者モブツからファイトマネーを引きだしてボクシング界でのし上がろうとし、モブツは自己の権力を世界にアピールしようとする。ザイールの国民たちは、「黒人の故郷に戻ってきた」というアリを熱狂的に歓迎する。 この様々な思いが錯綜する世界のなかで、アリとフォアマンの姿は見事に対照的である。フォアマンにとっては、トレーニングと、そして何よりもリングの上がボクサーとしての闘いの場であり、すべてだが、アリにはそうではない。といってもこれは、闘いがリングに立つ前からすでに始まっているというような駆け引きのレベルの話ではない。アリは常にむき出しの感情と生身の肉体で挑発的な磁場を作り、自分の神話に拮抗し、人々によって外から作られることを徹底して拒みつづける。 先述した『モハメド・アリの道』のなかには、アリのこんな言葉が引用されている。「おれはあんたたちが望むとおりの人間になる必要はないんだ」。アリは、偉大なボクサーであり、黒人たちの英雄であり、60年代のヴェトナム反戦運動の象徴でもある。しかし筆者はそれ以前に、まず何よりもこの言葉の究極の実践者であることが、アリという人間を特別な存在にしているように思う。この映画には、そんなアリの魅力が浮き彫りにされているのだ。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||