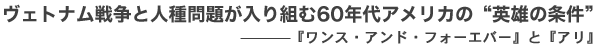 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (初出:「Cut」2002年5月号 映画の境界線10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ランダル・ウォレス監督の『ワンス・アンド・フォーエバー』とマイケル・マン監督の『アリ』は、その内容を対比してみると実に面白い。この2本はともに実話の映画化で、60年代のアメリカをまったく対照的な視点からとらえている。そのために、一方の作品だけではもうひとつ見えにくい時代や状況が、並べてみることによって鮮明になってくるのだ。 ヴェトナム戦争を題材にした『ワンス・アンド・フォーエバー』では、北ヴェトナム兵とアメリカ兵による最初の大々的な衝突といわれるイア・ドラン渓谷の"ランディング・ゾーン/X‐レイ"における戦いが描かれる。 1965年11月14日、ハル・ムーア中佐の部隊は、敵情の分析も不十分なまま、命令によってそこに送り込まれる。約400名の部隊は瞬く間に2000名のヴェトナム兵に取り囲まれ、壮絶な死闘を繰り広げる。映画は、接近戦が大半を占める戦闘を、ドキュメンタリー・タッチで生々しく浮き彫りにする。 『アリ』では、神話的な存在であるモハメド・アリの人生のなかでも、最も波乱に満ちた10年間が描かれる。22歳のカシアス・クレイは、64年2月のタイトルマッチでヘビー級の新チャンピオンとなる。 マルコムXと親交を深めていた彼は、黒人組織"ネイション・オブ・イスラム"の一員となり、指導者イライジャ・モハメドから"モハメド・アリ"の名前を授けられ、世間から危険視される存在となる。67年、ヴェトナム戦争への徴兵を正式に拒否した彼は、連邦大陪審から有罪を宣告され、リングからも締め出され、厳しい批判のなか孤独な闘いを強いられる。 2本の映画の接点は、ヴェトナム戦争とアリの徴兵拒否だと思われるかもしれないが、決してそんな単純なものではない。60年代にヴェトナム戦争と人種問題は非常に深い結びつきを持っていた。 その事実は、『ワンス・アンド・フォーエバー』のドラマにも反映されている。特に注目したいのは、これから戦場に向かう兵士たちと残される妻たちの世界では、人種問題について明確な温度差があることだ。 戦闘訓練で上官は、黒人兵の足の状態まで気づかい、全員がひとつの家族なのだと語る。兵士たちは、戦う人間に人種や宗教の違いなどないという言葉とともに戦場に送り出される。一方、兵士の妻たちの集いでは、ある世間知らずの妻が、ランドリーの白人専用の掲示を洗濯物の白物と勘違いする発言をし、少数の黒人を含む妻たちの失笑を買う。 この温度差は、皮肉にもアメリカのなかで軍がいち早く人種隔離政策の撤廃に踏み切り、人種統合を進めていたことを象徴している。つまり、アメリカの一般社会ではいまだ人種差別がはびこっていても、戦場では平等なのだ。「誰ひとり置き去りにしたりはしない。その者が生きていようと死んでいようと…。我々は全員そろって家路につく」。これは部隊を率いる主人公ハル・ムーア中佐の言葉だ。 先月号で筆者は『ブラックホーク・ダウン』について、こう締めくくった。「いまのところアメリカで平等の理念が最も現実味をおびるのは、どこにもない異境のなかで敵の激しい攻撃にさらされるときでしかないのだ」。ソマリアとヴェトナムという違いはあるが、この映画も戦闘は3日間という短期的な局地戦であり、敵に完全に包囲されて劣勢に立たされ、いかなる犠牲を払っても仲間や部下を救おうとするドラマが描かれる。 この類似は偶然ではない。貧富の格差を生む不平等な市場主義が支配する現代のアメリカでは、戦場でしか平等を夢見ることができない。『ワンス・アンド・フォーエバー』は、『ブラックホーク・ダウン』のようなエキゾティックな異境ではなく、歴史的な事実にそんな現実を投影しているのだ。 一方『アリ』は、このヴェトナム戦争と人種問題のリンクを対極の見地からとらえてみせる。批評家マイク・マークシーが書いた「モハメド・アリとその時代」は、60年代のアリを多面的に掘り下げる興味深い本だが、そのなかにこんな記述がある。「つまりヴェトナムの戦場では人種統合が現実となっていたのである。しかしそれは残忍で偽善的であり、黒人にとっては社会的前進ではなく、屈辱の上塗りをされたようなものだった」 アリの波乱の10年間を歴史的に整理してみると、彼がヴェトナム戦争と人種問題の狭間を生きていたことがよくわかる。『アリ』は、アリと親交があったサム・クックのステージから始まるが、クックはアリがチャンピオンになった64年の末に射殺される。黒人指導者のなかでいち早く反戦を訴えたマルコムXは65年2月に暗殺され、同じ月にアメリカは北ヴェトナムへの空爆を開始し、つづいて陸戦部隊が展開を始める。 アリは徴兵拒否のために67年末から3年半、リングから締め出される。後に反戦を訴えるキング牧師が暗殺されるのは68年。休戦協定が調印されるのが73年で、『アリ』のクライマックスとなる"キンシャサの奇跡"はその翌年の74年の出来事である。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
