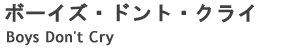 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (初出:「eiga.com」2000年6月、加筆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
女性監督キンバリー・ピアースにとって初の劇場用長編となる『ボーイズ・ドント・クライ』は、ブランドン・ティーナの実話がもとになっている。1993年、ネブラスカ州フォールズ・シティの町外れにある農家で、ふたりの女性の死体が発見された。被害者のひとり、ブランドンは、性同一性障害という苦悩を背負い、男として生きる道を選んだ。彼は女性たちの人気者になったが、この秘密が明らかになったときから、悲劇が始まり、死体で発見されることになった。 監督のピアースは、この作品を作るにあたってインスピレーションを得たもののひとつに、ノーマン・メイラーの『死刑執行人の歌』をあげている。筆者もこの映画を見ながらこの本の世界が頭をよぎった。 メイラーが自ら”事実に基づく小説”と呼んだこの作品に描かれるのは、ゲイリー・ギルモアの物語である。10代半ばから犯罪を繰り返し、前科を重ねたギルモアは、最後に仮釈放になった76年に、明確な動機もなくふたりのモルモン教徒を射殺した。 アメリカ中を騒然とさせたのは、そんな彼が自ら死刑を要求し、翌年の1月に処刑されたことだ。それはある意味で、誰にも彼を罰することはできないという挑戦的な姿勢でもあった。 『死刑執行人の歌』には、その最後の仮釈放から処刑に至る9ヶ月間のギルモアと彼に関わった多くの人々の活動が克明に綴られている。 そのギルモアの物語とこの映画がどう結びつくのか不思議に思う人もいることだろう。筆者がまず注目したいのは、ギルモアとこの映画の主人公ブランドンに対する激しい憎悪の源である。『死刑執行人の歌』のもとになる取材を行ったローレンス・シラーは、ギルモアについてこう考察している。 「頭がおかしくて正気でないような殺人鬼なら世間は受け入れられる。だが殺人鬼が主導権を握るようになったら――それがギルモアに対する激しい憎悪を多く生み出していた」 もちろんブランドンは殺人鬼ではない。しかし彼の存在は、ギルモアに通じるオーラを放っている。ブランドンの正体を知ったとき、ジョンやトムは彼を化け物呼ばわりする。しかし彼らが、本当にブランドンのことをただ化け物とか変態だと思っているのなら、あれほどの憎悪は生まれない。彼らは、ブランドンに男として主導権を握られたことが耐えられないのだ。 だから、ブランドンを女として徹底的に辱めることで主導権を奪い返そうとするが、 それでも奪い返せない存在感が彼にはある。それが彼らの男としての存在に揺さぶりをかける。この映画には、そんな加害者たちの心理もしっかりと描きこまれている。 そしてもうひとつの共通点がある。ギルモアには彼を無条件に受け入れた恋人がいて、『死刑執行人の歌』は、過去も未来もない現在に花開いた彼らの純愛の物語にもなっている。『ボーイズ・ドント・クライ』もまた、ブランドンと秘密を知りながら彼を無条件に受け入れたラナの純愛の物語になっているのである。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||