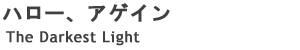 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (初出:「Movie Gong」Vol.15、2001年春号、若干の加筆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
筆者のお気に入りの脚本家サイモン・ボーフォイは、監督にも進出したこの『ハロー、アゲイン』で、テーマ的にこれまでの作品よりも一歩踏み込んだ世界を作り上げている。
The Darkest Light trailer from Footprint Films on Vimeo. 『フル・モンティ』や『マイ・スウィート・シェフィールド』では、仕事にあぶれた労働者たちが、ストリップを始めたり、誰もやらない送電線のペンキ塗りを引き受ける。しかしその結果、彼らが本当に得るものは、金ではなく、失われかけたコミュニティの絆や労働者としての誇りである。ボーフォイは、サッチャリズムによって切り捨てられ、苦境に立つ人々を身近な視点でとらえ、 金だけがすべての社会の中で、本当に大切なものを独特のユーモアを交えながら描きだしてきた。 新作について彼は、「お金では私たちが新世紀に向かって抱える問題は解決しない」と語っている。つまり、現代社会だけではなく、もっと先のことを見つめようとしているのだ。 ヒロインである少女キャサリンの生活は決して楽ではない。彼女の弟は白血病で予断を許さない状況にある。牧畜を営む彼女の両親には、家畜が口蹄疫に感染するという災厄がふりかかる。ボーフォイは、ヨークシャーの風景を通して、彼らが不安定な世界を生きていることを暗示する。荒涼とした大地には、風力発電機が立ち並ぶかと思えば、古びた軍の射撃演習場があり、戦闘機が突然、低空飛行してきて、激しく空気を切り裂く。 キャサリンはそんな混沌とした世界のなかで、インド系の親友ウマから聞かされたヒンドゥー教の教えに素朴な関心を持ち、やがて彼女たちは奇妙な光に遭遇する。そしてキャサリンは奇跡が起きることを確信し、住人たちもその光にすがろうとする。 しかしボーフォイは現実離れした奇跡を描いたりはしない。ここで起こる出来事はあくまで生活に根ざしている。ドラマは、キリスト教やヒンドゥー教などの教義の枠を越えた、前向きな日常の営みの中に、奇跡が起こることを物語る。キャサリンが、最初は敵意をおぼえていたインド系のウマを受け入れ、彼女の文化を共有するようになった時点で、そこに奇跡の種は蒔かれていたのだ。
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||