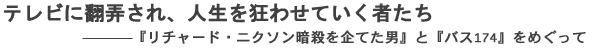 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (初出:「Cut」2005年6月号 映画の境界線46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ニルス・ミュラー監督の長編デビュー作『リチャード・ニクソン暗殺を企てた男』の物語は、70年代に起こった実話に基づいている。主人公サム・ビックは、アメリカの夢にとり憑かれた男だ。客を欺くようなセールスマンの仕事に苦痛を覚える彼は、独立して成功を収め、別居中の妻子を取り戻すことを夢見るが、努力は報われない。 孤立する彼の頭のなかでは、ウォーターゲート事件を起こしたニクソンが、アメリカの夢を踏みにじる許しがたい存在となる。彼は、民間機をハイジャックしてホワイトハウスに墜落させる暗殺計画を立て、空港へと向かう。 99年に企画がスタートしたこの作品は、必ずといっていいほど9・11と結びつけて語られる。確かに9・11によって暗殺計画はよりリアルなものとなる。だが、サムはどこにでもいる平凡な男だ。 そういう意味で、もうひとつ注目すべきなのが、奇しくも企画がスタートしたのと同じ年に起こったコロンバイン高校銃乱射事件だろう。事件を起こした二人組は、飛行機をハイジャックしてニューヨークに墜落させるというテロ計画も考えていたからだ。そんな事実と重ねることで、この映画は現代的な意味を持つ。 しかし、もっと重要なのは、歴史を検証しようとする視点だ。監督のミュラーは、サムの存在を知る以前に、偶然にも彼とそっくりな架空の人物を主人公にした脚本を書いていた。その脚本では、暗殺の対象はニクソンではなくジョンソンだったが、そこには深い意味がある。 脚本のきっかけになったのは、テレビで見た64年の大統領選に関するドキュメンタリーだった。60年の大統領選で、ケネディがニクソンとの初のテレビ討論会で形勢を逆転したことはよく知られている。だが、そのドキュメンタリーを見たミュラーは、テレビの影響力が完全に認知された64年のジョンソンとゴールドウォーターの大統領選こそが、本質が失われ、表層に支配される決定的な分岐点だったと考えた。 つまり、暗殺の対象となるジョンソンとは、そんな表層を象徴していたのだ。そして、その脚本に関するリサーチを進めるうちに、サムという実在の人物を見出し、彼の物語を語るために時代背景を64年から74年に変えた。しかし、本質的なテーマは変わっていない。 孤立していくサムには、機械工の友人以外に話し相手もなく、あとはテレビを通して世界を見るしかない。そのテレビには、声明を読み上げるニクソンばかりが映し出される。 彼は、尊敬するレナード・バースタインのレコードを聴き、彼に送るためにテープにアメリカの現状に対する自分の考えを録音する。テレビで見たブラック・パンサーの闘士に共感した彼は、その事務所を訪ね、カンパをするが、政治的な人間ではないために浮いてしまう。ニクソンに対する怒りと憎しみが抑えられなくなっていく彼は、ホワイトハウスの庭に着陸したヘリのニュースを見て、暗殺計画を思い立つ。 彼はテレビのなかのニクソンを憎み、テレビで見たものを組み合わせて計画を立てる。彼が暗殺しようとするのは、生身のニクソンではなく、テレビのなかのニクソンであり、それをさらに突き詰めるなら、夢を踏みにじるような偽りのロールモデルを生み出すメディアそのものなのだ。 だからこの映画は、ニクソンを演じる俳優を必要としない。空港で銃を振り回し、突進する彼は、すでにその標的を失っている。メディアを暗殺しようとした平凡な男は、家族や友人にも振り向かれないようなニュースに封じ込まれ、忘れ去られていくことになるのだ。 そして、この映画と対比してみると興味深いのが、ジョゼ・パジーリャ監督のドキュメンタリー『バス174』だ。これは、2000年6月にリオデジャネイロで、20歳の若者サンドロが引き起こしたバスジャック事件を、関係者たちの証言を交えながら詳細に検証し、ブラジル社会の暗部を抉り出そうとする作品だ。 サンドロの生い立ちは悲惨だ。スラムに生まれ育ち、子供の頃に母親が刺殺されるのを目撃し、警察の仕業とされるカンデラリア教会のストリート・チルドレン虐殺事件を体験し、シンナーやコカインに依存し、劣悪な環境の少年院に収監されていた。しかし、そんな境遇に絶望してバスジャックに走ったわけではない。
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||