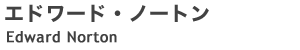 |
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| (初出:「English Journal」2004年1月号) | |||||||||||||||||||||||
|
エドワード・ノートンは、デビュー作『真実の行方』の新人離れした演技で映画人や観客を驚嘆させ、いきなりアカデミー助演男優賞にノミネートされるという快挙を成し遂げた。この映画で彼が演じたのは、大司教惨殺事件の容疑者アーロン。気弱であどけなさすら漂わせる容疑者と面会した弁護士は無実を確信するが、その若者は、極度の緊張を強いられると邪悪で凶暴な人格に豹変する。ノートンは、鬼気迫る演技で二重人格者に成りきり、しかもラストでは弁護士を完膚なきまでに打ちのめしてしまうのだ。 ノートンの圧倒的な演技力は、彼が演じるキャラクターが見せる複数の顔や人格によく現れている。『アメリカン・ヒストリーX』のデレクは、激しい怒りと憎しみに駆り立てられるスキンヘッドの白人至上主義者だが、刑務所のなかで、ある黒人の囚人と、白人と黒人ではなく個人と個人として絆を深めることによって、変貌を遂げていく。『ファイト・クラブ』で不眠症に悩まされるジャックの行動は、彼の前に現れた謎の男タイラーの正体が明らかになることによって、別な意味を持つことになる。『スコア』で税関に保管された秘宝の強奪を企むジャックは、知的障害者を装い、清掃員として雇われることで、税関の内部に潜入している。『レッド・ドラゴン』のFBI捜査官グレアムには、「わたしたちが瓜二つだから」というレクター博士の言葉が重くのしかかり、実際、冷酷な一面も覗かせる。 しかしもちろん、ノートンは、演じがいのある複雑なキャラクターばかりを追い求めているわけではなく、作品のテーマにもこだわっている。特に『ファイト・クラブ』に対する思い入れは強い。ひたすら消費しつづけるだけの生活のなかで、生きている実感すら得られない主人公は、現実と妄想の狭間に激しい闘争の場を作り上げ、やがてそれが消費社会に対するテロにまで発展していく。そんなドラマには、文化の多様性や地域性を奪い、人間や社会を画一化していく市場主義に対する鋭い批判が盛り込まれているのだ。 |
|
||||||||||||||||||||||
