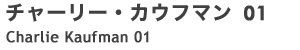 |
||||
|
||||
| (初出:「STUDIO VOICE」2001年8月号) | ||||
|
「マルコヴィッチの穴」をユニークな作品にしているのは、まず何よりも脚本だ。7と1/2階にあるオフィスや15分だけマルコヴィッチになれる穴という発想は、まさにユニークとしか言いようがない。しかし、決してただ奇抜さだけで勝負しているわけではない。 この作品でカウフマンの発想のヒントになっているのは、エミリ・ディキンソンの詩であるように思える。映画の冒頭近くに、そのディキンソンの巨大な人形を操るパフォーマンスが出てくる。この十九世紀の女流詩人は、フロンティア精神が外部に向かう時代に、それを自己の内面に向かって発揚するようなヴィジョンを打ち出した。さらには、自己という王国を外的から守ることは容易いが、己という内なる敵には無防備であるため、自らの意識を征服しなければならないと主張した。この映画では皮肉なことに、その詩人の人形が他人に操られ、見世物になっている。 カウフマンの面白さとは、たとえばそんな十九世紀の視点をいきなり引き出し、現代の状況に半ば強引に照らし合わせ、読み直し、独自のドラマを紡ぎだすところにある。現代では、自分がどう見えるかがすべてであって、もはや誰も内面など気にしない。プライバシーすらメディアに消費され、自己を演じる領域と化している。それをディキンスン的な視点で語りなおしてみると、マルコヴィッチの穴になる。そして穴を出てみるとそこには、表層的な生活を演じるサバービアに向かうフリーウェイが待っているのだ。 ミシェル・ゴンドリが監督したカウフマンの新作『Human Nature』では、野生のなかでサルとして育った男と、彼を上流社会に適応させようとする科学者、その科学者の恋人で、男の過去と自由を守ろうとする動物学者の奇妙な三角関係が描かれるという。これも、たとえばE・R・バロウズの「類猿人ターザン」にあるような近代の視点に対するカウフマン的な読み直しを予感させる。 |
|
|||