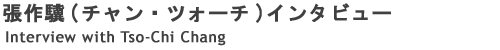 |
||||
|
||||
|
|
||||
| (初出:「キネマ旬報」2000年9月下旬号) | ||||
|
|
||||
|
映画「最愛の夏」の出演者は、実際に視覚や知的に障害がある人々を含め、すべてアマチュアの役者たちで占められている。アマチュアを積極的に起用する映画では、いま、ここにあることのリアリティを重視するのが一般的だが、チャン・ツォーチの場合は違う。 「ぼくはアマチュアの役者を使っても、即興とかその場の状況に委ねるような作り方をしたことはない。あくまで自分のヴィジョンがあって、それに近づいてもらうように努めています。ぼくがアマチュアの役者たちと最初にすることは、いつも一緒にご飯を食べることです。彼らを見ながら、それぞれがどんな悩みを抱え、どんな背景を持っているのかを考え、 脚本を書き直すこともあります。こちらから要求を出しすぎれば、彼らが押しつぶされてしまいますから。アギィ役のように知的障害がある人の場合には、普通ならNGになるカットを使うこともあります」 この映画で印象的なのは、いまとここではなく過去と未来、特に過去だ。ヒロインの父親は、死期が近いことを悟ったとき、大切な記憶を自分の身体でもう一度確認しようとする。ヒロインは、窓の向こうに自分の憧れを投影し、やがてそれは大切な記憶に変わる。チャン監督は登場人物たちを過去と未来のはざまにある存在としてとらえているのだ。 「映画を作っているときにはそんな意識はありませんでしたが、あらためてそう言われてみると、それがぼくの人生観であるように感じます。ぼくが脚本を書くとき大事なのは、自分の過去を振り返ることです。脚本のなかで背景や設定は変わっても、自分の追想に頼っている部分が大きい。この映画もさかのぼってみれば、追想というものを意識するところから作品ができていると思います」 彼が意識する追想は、ドラマの細部にまでしっかりと反映されている。たとえばヒロインが恋をする少年アピン。母親を亡くし、父親が大陸に戻ってしまい、〝外省〟として疎外される彼は、人気のない海の岩場で、木の棒で空に向かって小石を打ちつづける。 |
| |||