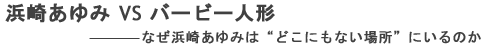|
浜崎の受賞理由は以下の通りだ。「2000年2001年と、歌を初めとする創作活動、歌唱力および圧倒的なファッション・センスで多くの女性に今最も影響力を与えている女性アーティストである浜崎あゆみさんは、常に世界の女性のファッション・リーダーであり時代を着こなしてきたBarbieに、そのイメージが日本女性として最も近い存在であると同時に、その思想や世界観を体現できる存在であること」。
なるほど正論である。が、こうしてバービーと浜崎が結び付けられてみると、筆者にはふたつの存在がもっと深い部分で共鳴しているように思えてくる。
■■アメリカを代表するイコンと少女たちの複雑な関係■■
バービー人形は、1959年にニューヨークの玩具見本市でデビューした。そのうたい文句は「スタイル抜群の10代のファッション・モデル」。衣装を着せ替えることで、何にでもなれるこの人形は、バービー現象を引き起こし、スターに負けないファッション・リーダーとなり、20世紀後半のアメリカを代表するイコンとなった。
それだけの影響力を持てば、当然、批判も出てくる。バービーは、物質主義の象徴として、あるいは、アメリカ人の女性像を規定するものとして攻撃にさらされた。また、俗物の仲間入りも果たした。20世紀アメリカの俗物を集大成したジェーン・マイケル・スターンの「悪趣味百科」で、バービーの頁はこんなふうに始まる。「バービーはおつむが空っぽ。彼女は飛び抜けた肉体派、ショッピングセンターを徘徊するブランド種族だ」。
このように、その存在があまりにも大きくなってしまうと、良くも悪くも一面的な見方をされがちになるものだが、コラムニストのM・G・ロードが、バービーとアメリカ社会の関係を跡づけた「永遠のバービー」を読むと、バービーとそれを所有する少女たちの関係がもっと複雑なものであることがわかる。彼女は、「子供たちの内面生活においてバービーが象徴しているものは、指紋と同じく一人ひとりまったく異なる」と主張し、彼女自身の体験も含めたいくつかの実例を挙げている。
ロードの母親は彼女が8歳の時に乳癌で乳房を切除し、以来バービーの豊かなバストは破滅の象徴となった。さらに彼女は、乳癌で死亡する女性が決して少数派ではないことを強調する。黒人のジャーナリスト、スーザンは、バービーにクリスティ(70年代に登場)のような黒人の友達がいるのが、とても意味のあることだったと語る。アジア系のジャンは、母親がバービーの妹のスキッパーしか与えなかったため、人形遊びを卒業しても自分が脇役だという思いから逃れられなかった。
■■伝統も歴史もない時代と自分の証としての過去■■
ここで筆者は、3つのことに注目してみたい。第1に、バービーや彼女の仲間の人形とその持ち主は、一対一の関係を構築し、その関係は決して一様ではない。第2に、ロードが「バービーを見ていると、遠い昔の感情に火がついた」とも書いているように、バービーはその持ち主が過去への扉を開く役割を果たしている。第3に、本書で直接言及されているわけではないが、その過去が持つ意味である。本書が書かれた90年代半ばには、すでに冷戦構造が終わりを告げ、市場万能主義が世界を覆っている。伝統や歴史は意味を失い、拡大する消費社会が生活を均質化し、個人のアイデンティティは揺らいでいく。そんな状況のなかで、指紋のように異なる過去は、自分であることの証として特別な意味を持つことにもなるはずだ。
バービーをめぐるこの3つの要素が、浜崎の世界に結びつくと筆者は思うのだが、具体的にどう結びつくのかは、3番目の要素から逆にたどっていく方が、わかりやすいだろう。
日本のアーティストのなかで、現代という時代を肌で感じ、それを作品に反映しているのはもちろん浜崎だけではない。しかし彼女は、この現実を非常に自覚的にとらえ、独自の世界で自己を探求している。昨年のツアーの第二幕が物語るように、彼女の世界のなかでは、「楽園の創造、生命の誕生」という夢見るような出来事から、時空は一気に「いま、ここ」へと至る。彼女は伝統も歴史もない現在に、突然、放り出され、しかも漠然とした未来を夢見ない彼女にとって残された時間はきわめて限られている。だからこそ彼女は、様々にかたちを変えながら、徹底して過去というものを掘り下げていく。過去が喪失やトラウマに満ちていても、それが自分であることの唯一の証であり、それなくして自分の未来はあり得ないからだ。
■■"どこにもない場所"の住人であろうとする浜崎■■
浜崎の世界に共感を覚えるリスナーは、自分の過去を振り返り、それを彼女の過去に重ね合わせることだろう。そういう意味で彼女の歌は、閉ざされた過去への扉を開く役割を果たす。しかし彼女は、そうした共感に対して一線を引き、リスナーを突き放す。君の過去と僕の過去は同じではない。人は決して同じ孤独や同じ心の傷を抱えているのではない。振り返った過去から何を引き出し、自分の未来を切り開くのかは、<Depend on you>=あなた次第なのである。
共感という感情のもとに、自分の過去を浜崎の過去に重ね、彼女の物語を生きることからは、何も生まれない。各自が過去を掘り下げ、むしろ違うことが明らかになるところから、共感は意味を持ち始めるのだ。未来ではなく、過去にある"それ"に気づくことを、あえて<Duty>=義務という重い言葉で表現するのは、それが個人的な作業であることを強調するためだろう。そして浜崎は、<SURREAL>の詞にあるように、「どこにもない場所で/私は私のままで立っている」。この"どこにもない場所"が、彼女が引く一線なのだ。
また、浜崎の詞には、「〜かもしれない」とか「〜なのでしょう」のように曖昧な印象を与える表現が目立つ。しかも、そうした表現ゆえに、「君」とか「僕」といった言葉が指し示すものが、変化し広がりを持つ。この曖昧さを否定的にとらえる向きもあるだろうが、筆者は彼女ならではの前向きな表現であると思う。なぜなら、曖昧であることによって、リスナーは自分で答を選択しなければならなくなるからだ。教祖であれば、答を示すのかもしれない。しかし、彼女はそんな教祖ではないし、違う過去を背負う人間に共通の答などあるはずないのだ。彼女はそんなふうにして、集合的な共感を暗に拒み、リスナーと一対一の関係を構築しようとする。
筆者はこの文章の冒頭で、どこか人間離れした浜崎のイメージについて書いた。その記述は、彼女の表層だけに注目し、並べたてているように見えたかもしれない。しかし、彼女のイメージは彼女の姿勢や内面と深く結びついている。彼女が、次々と姿を変え、「どこにもない場所」の住人であろうとすることは、クールでも斜に構えているわけでもなく、彼女の誠実さの現われなのだ。
|