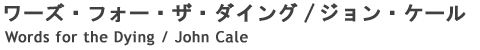|
このアルバムの発端について解説すると、ジョンは最初、オペラを書こうという構想を持っていた。自分の過去、自分がどこから来たのかということを何らかのかたちで表現したいと思っているうちに、
ディラン・トマスの生涯を主題としたオペラというアイデアが浮かんできた。そこで、詩だけではなく、ディラン・トマスの伝記にも目を通し、この詩人の人生のなかで詩というものが果たした役割を理解し、
それから、彼の詩に音楽をつけてみようということになった。
このディラン・トマスの詩にインスパイアされた大作が、<フォークランド組曲>になっているのは、ディラン・トマスの作品のなかから音楽化する詩をセレクトしているときに、
フォークランド紛争が起こったことによる。ジョンは、作品をフォークランド紛争にも見合うものにするために詩の言葉のひとつを変え、この紛争による両国の死者に捧げる内容にしてもいるという。
この組曲の演奏は、ソヴィエトのオーケストラによるものだが、どうしてソヴィエトのオーケストラを使うことになったのかということについては、
アルバムのプロデュースをしているブライアン・イーノと深い関係がある。ジョンが書いたこの作品がとても気に入ったイーノは、夫人がソヴィエトの官僚につてがあったことから、
ソヴィエトのオーケストラでいけるのではないかとジョンに提案し、話がまとまったのだった。
アルバムの最後に収録されている<ソウル・オブ・カルメン・ミランダ>にもイーノが絡んでいる。この曲は、<フォークランド組曲>の製作中に、ジョンがイーノといっしょにたったの3時間で曲も詞も書き上げてしまった作品だそうだ。
そこで、それならアルバムを一枚作ってしまおうということでできあがったのが、すでに日本でも発売されているジョンとイーノの共作「ロング・ウェイ・アップ」なのだ。但し、このバルバムに収められた曲が、
すべてあっという間にできあがってしまったわけではなく、実際にはだいぶ苦労したようである。
また、このアルバム「ワーズ・フォー・ザ・ダイング」には、同名のドキュメンタリーが製作されてもいる。その内容の軸になるのは、モスクワにおけるレコーディング風景だが、全体の構成は、
ジョン・ケールのキャリアの集大成といえるような内容になっている。たとえば、このドキュメンタリーは、ヴェルヴェット・アンダーグラウンド時代の映像や写真で幕をあけ、ジョンのアヴァンギャルドなソロ・パフォーマンスにつづき、
これまでのキャリアが簡単に紹介され、モスクワへの旅が始まる。また後半では、ジョン・ケール夫人へのインタビューや子供も交えた家族の映像、そしてジョンがウェールズに暮らす母親に会いにいく場面などまでが収録されているのである。
これはジョンにインタビューして知ったのだが、彼の母親は来日する2ヶ月ほど前に亡くなったそうだ。そして彼は、母親との再会をフィルムに記録できたことをとても喜んでいた。
このドキュメンタリーで最も印象に残るのは、ラストシーンである。ジョンは、ウェールズの崩れかけた古城と田園風景のなかに消えていく。そのバックには、<フォークランド組曲>の一部が流れる。
この場面を見ていると、この大作の深さとか壮大さというものが、いっそう身近に迫ってくるのである。
この場面は別の意味でも象徴的であると思う。どう象徴的なのかは、冒頭で触れたこととも関連するのだが、それを語るためには、ルー・リードとジョン・ケールの出会いにまでさかのぼる必要がある。
彼らが出会ったのは1964のこと。すでにハイスクール時代からバンド活動をしていたルー・リードは、当時ロックンロールのスターになることを夢見ながら、小さな音楽出版社でソング・ライターの仕事をしていた。
一方、イギリスの南ウェールズ出身で、幼い頃からクラシックの素養を身につけていたジョンは、当時、現代音楽を学ぶ留学生としてニューヨークに暮らし、仲間たちと様々な音楽の実験に熱中していた。ジョンは、
会社から見向きもされなかったルーの曲<ヘロイン>を聞かされ、魅了される。その後はご存知のように、ふたりはヴェルヴェット・アンダーグラウンドを始動し、ウォーホルに出会い、あのバナナのジャケットのデビュー作を発表する。
しかし、ふたりの関係は長くつづくことはなかった。ジョンは68年9月にバンドを脱退する。アルバムでいうと、ヴェルヴェットの2作目にあたる「ホワイト・ライト/ホワイト・ヒート」までだ。その理由のひとつには、
あくまでアヴァンギャルドなサウンドを追い求めるジョンと、詞や歌に比重を置くルーとの確執があげられる。「ホワイト・ライト〜」の最後を飾る有名な<シスター・レイ>は、17分あまりにわたって延々とつづく単調なリズムにのって、
制御を失った暴力的で混沌とした世界が紡ぎだされ、ジョンの影を色濃く感じさせる。
後にルー・リードはジョンの脱退について、「あいつは、音楽のことを知り尽くしているし、確かに偉大なミュージシャンだ。とても普通じゃない…それは、あいつがウェールズ人てことなんだ」という発言を残している。
話は少し飛ぶが、筆者はウォーホルが、アメリカの大量消費時代の破壊的な力、破局の予兆を、毒々しく強迫観念的に対象化し、アートとして成立させたのと同じように、スタイルはまったく違うが、
ヴェルヴェット・アンダーグラウンドも都市に潜むコントロールしがたい力を音楽を通して強迫観念的に描いていたと思う。そして、ウォーホルは、典型的なアメリカ人の視点と移民の視点を持っていたが、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの場合も、
<シスター・レイ>のような曲に現れる強迫観念というのは、ルーのアメリカ人の視点とジョンの異邦人、ウェールズ人の視点の激しい拮抗から生み出されていたように思えてならない。
そしてふたりが、「ソングス・フォー・ドゥレラ」で再び激しい火花を散らしたとき、彼らはそれぞれにルーツを確認しようとしていた。あくまでニューヨークにこだわるルー・リードに対して、ジョン・ケールはこの「ワーズ・フォー・ザ・ダイング」というアルバムを通して、ウェールズ人としての自己に深く分け入っていたのである。 |