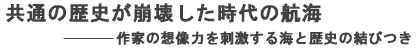 |
|||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| (初出:「paperback」Summer 2001 Vol.2、若干の加筆) | |||||||||||||||||
|
たとえば大航海時代が端的に物語っているように、かつて世界の歴史の流れは海に支配されていた。それは遠い過去のことだが、海と歴史の深い結びつきは、作家の想像力を刺激し、過去ではなく現代における個人と歴史の関係を問い直すような興味深い物語を紡ぎ出す。 ウンベルト・エーコの「前日島」の時代設定は1643年。ヨーロッパ人にとって未知の島々がまだ数多く残されている時代だ。また当時は、経度を正確に割り出す技術がなく、たとえ楽園のような島を発見して、故郷に錦を飾ったとしても、再びその楽園に到達できるという保証はどこにもなかった。この小説のなかにはこんな台詞がある、「いったん大海に出れば、盲人が盲人の手をひいて歩いているような状況だということです」。 主人公ロベルトは、枢機卿のスパイとなってあるオランダ船に乗り込み、経線計測の秘密を探り出そうとするが、船は南太平洋で遭えなく難破。泳げない彼を乗せた戸板は、美しい島の入り江に碇を下ろすダフネ号に流れ着く。無人と思われた船には、唯一の生存者である神父が隠れていて、ダフネ号も同じ目的を持っていたことが判明する。さらに神父は、その船と目の前に見える島の間に、グリニッジを本初子午線に設定した場合の対子午線があることを明らかにする。 冷静に考えれば、そこに日付変更線があるからといっても驚くほどのことではない。しかし、宗教から科学まで豊富な知識を持つ神父は詭弁を弄し、子午線を驚きに変えていく。ロベルトは、前日と翌日を分けるこの一本の線を越えることができれば、24時間前の世界にたどり着けると信じ込む。取り戻すことができない過去という時間が、かたちある島となって現れる。その島は、二度と会うことができない愛しい女性の世界となり、果てはユダがキリストを救い出せる世界ともなる。 この小説は、エーコならではのバロック的な迷宮世界が広がり、読者によって様々な解釈ができる。そのなかでも筆者が印象的だったのは、近くて遠い前日島を前にして、ロベルトが小説を書き出すことだ。彼はこんなふうに考える、「現実の世界で自分に何が起こったのか。それを理解するためにも、自らの手で、これまでの出来事の<歴史>を再考して、裏に隠された原因と動機を見つけなければならない。自分たちが読む<歴史>ほど不確かなものはない。それに比べれば<小説>のほうが、より確かな何かがある」。 子供の頃から存在しないはずの兄というドッペルゲンガーを創造し、逃げ道にしていた彼は、愛しい女性と兄を主人公にした物語を描き、自分の想いを果たそうとする。そして、物語のなかで兄と一体化し、愛を手にするだけでなく苦難を乗り越えていく。この前日という空間に集約されていく<歴史>とそこから紡ぎ出される<小説>の関係、あるいは距離が、この「前日島」をより現代的な作品にしている。 それは、行動派の作家としてカルト的な人気を誇るウィリアム・T・ヴォルマンの「ザ・ライフルズ」と比較してみると、もっと明確になることだろう。この作品は、いくつかの歴史的な事実が、膨大な資料をもとに詳細に読み解かれながら、同時に時空を越えた小説に収斂されていく。 歴史的な事実の軸になるのは、イギリス人のジョン・フランクリン卿が、19世紀前半に繰り返し挑んだ北西航路遠征である。その最後の航海で、フランクリン率いる2隻の艦船は、3年に渡って北極海の氷に閉じ込められる。食料が底をついたため、探検隊は艦船を放棄し、人肉まで糧として氷の世界に活路を見出そうとするが、結局全滅してしまう。もうひとつの軸になるのは、今世紀半ばに、カナダのケベック北部に暮らしていたエスキモーたちが、白人によって強制的に辺境の地に移住させられ、劣悪な環境での生活を強いられたという出来事だ。 遠征隊は望んで死地に赴きながらも、いざとなれば親切なエスキモーたちが救いの手を差し伸べてくれると信じていた。その百年後、エスキモーたちは死地に等しい辺境に強制的に隔離され、白人は救いの手を差し伸べようともしなかった。そんな彼らの皮肉な運命には、「何の制約もなく、技術すら不要な武器」であるライフル銃が、伝染病のように極北の地に広がったという事実も、暗い影を落としている。 |
| ||||||||||||||||