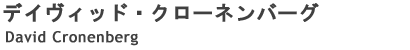|
妻を射殺し、失う。映画「裸のランチ」は、そうした欠落からドラマがひもとかれることになった。主人公リーは、 失った妻の正体を握っているかのようなカブトムシ・タイプライターから逃れることができず、何者かにあやつられるがままにタンジールへと旅立っていく。
■■幻のタンジール■■
クローネンバーグの「裸のランチ」は、冒頭でも触れたように、当初、タンジールでの撮影からスタートすることになっていた。しかし、湾岸戦争の影響で、それは不可能なことになってしまった。
「わたしたちはタンジールで撮影しなければならないと思い込んでいた。というのもそこがバロウズが『ネイキッド・ランチ』の大部分を書いたところだったから。
でもタンジールに行けないことになって脚本を読み直してみると、セットを作り非現実的にし(て内面性を深め)た方がこの脚本にはふさわしいことに気付いた。 映画のなかのたくさんのディテール、アイデアは、ロケが中止になってから浮かんできたものだ。たとえば、同じ窓の風景がときにタンジール、ときにニューヨークになっていただろう?
夢のような場所なんだ。湾岸戦争がよい結果をもたらしてくれたのさ」
こうして、「裸のランチ」の舞台は、五〇年代ニューヨークと幻想のタンジールを揺れ動くことになったが、光をおさえた陰影に富む色調で描きだされる舞台の雰囲気を映像の背後から支えている音楽の素晴らしさは無視することができない。
■■モロッコのオーネット・コールマン■■
クローネンバーグの作品は、これまで、音楽がとりたてて魅力的だったということはなかったが、この「裸のランチ」は例外だ。基本的に音楽を手がけているのは、クローネンバーグ作品のほとんどを手がけてきたハワード・ショアだが、
フリー・ジャズの創始者オーネット・コールマンが大きくフィーチャーされているのだ。音楽が、いつものようなオーケストラ・サウンドだったとしたら、ということは想像もしたくないが、音楽については、ハワードの功績が大きいようだ。
「それは、ハワード・ショアのアイデアだ。脚本が出来てすぐにハワードに送って話し合いはじめたから、音楽については長いあいだ話し合ったわけだ。わたしはジャズはこの登場人物にはとてもふさわしいと感じていた。
というのも彼らは当時、ラディカルだったからジャズはぴったりなわけだ。また、一方では、タンジールでロケするつもりだったからインターゾーンに北アフリカの雰囲気がある。だから北アフリカの音楽もひとつの可能性だった。
そしたらハワードが『ジャズと北アフリカの両方の要素を持った録音がある』と言って、それが、オーネット・コールマンが一九七三年に録音したものだと教えてくれた。そして、このアルバムをハワードが送ってくれたんだが、それを聞いて、
これこそインターゾーンの国家であるべきだと思った。ハワードは個人的にコールマンを知っていたから、もし君が、コールマンがもっとこの映画の音楽をやるべきだと思うなら、彼にコンタクトをとれると言った。
それで、それまでに撮影済みのフィルムをビデオにして彼に送ったんだ。彼はすごく気にいってくれて、この映画に係わることに賛同してくれた」
ハワードがクローネンバーグに送ったアルバムは、七七年に発表されたオーネットの傑作「ダンシング・イン・ユア・ヘッド」だ。このアルバムには、オーネットがモロッコのジュジューカの音楽家たちとレコーディングした<ミッドナイト・サンライズ>という七三年録音の曲が収録されている。
クローネンバーグが聞いたのはこの曲だ。ちなみに、この曲は、映画の幻想のタンジールのバックに流れ、当然、サントラにも収録されている。
舞台を考えたとき、この映画の音楽にこれほどうってつけのミュージシャンもいないのではないかと思うが、<ミッドナイト・サンライズ>に対するハワードの「北アフリカとジャズの両方の要素を持った録音」という表現は、
ほとんど映画にあった音楽と言っているにすぎず、大いに補足しておく必要がある。バロウズとオーネットはモロッコと音楽を通じてもっと深く結びついているのだ。
オーネットは、七三年一月、モロッコの山間にある村ジュジューカを訪れ、古来からの音楽の伝統を守り続け、民族楽器を演奏する地元のミュージシャンたちと出会った。バロウズの長大な評伝『リテラリー・アウトロー』のなかには、こんなことが書かれている。
「ジュジューカでは年に一回、牧羊神の祭がおこなわれ、これはバロウズが通う行事でもあった。特別のアトラクションでは、偉大なジャズ・サックス奏者オーネット・コールマンが熟達した演奏者たちのテクニックを学ぶために登場し、彼らと共演することになっていた。
[中略](演奏家たちに)オーネットが加わり、拮抗するハーモニーを作りあげたとき、バロウズには、自分が二千年間生き続けるロックン・ロール・バンドを聞いているように思えた。
カルタゴ時代から続く音楽とモダン・ジャズ、ふたつの表現が出会ったとき、音の新しいフロンティアが誕生したのだ」
そんなことを念頭においてこの映画を観ると、ゆらめくようなオーケストラやスピード感あふれるデナード・コールマンのドラムス、あるいは、エスニックなハーモニーやビートをバックに"ハーモロディック"にうねるオーネットのサックスが、
五〇年代ニューヨークから幻想のタンジールへと旅立つリーを彩る光景には何か感慨深いものがある。また、映画の最初の方の、リーが、バグパウダーを彼の妻の唇に塗ってくちづけする場面で、
オーネットのサックスとセロニアス・モンクの〈ミステリオーソ〉のメロディが交錯するあたりの幻想的なイメージなどもひどく印象に残る。
オーネットは、ジュジューカの音楽家たちとの出会いについて、こんなふうに書き記している。この内容は、ここまで書いてきたこととどこかで共鳴する部分が少なくないように思えるのだが、どうだろう。
「信じがたかったのは、彼らが西洋音階ではなく、調律もされていない楽器を演奏していたにもかかわらず、ユニゾンで演奏していたことだ。これは人類の音楽だ。これは、生命の状態を伝えているのであって、女に逃げられたとか、戻ってきてくれとか、
おまえなしに過ごす夜は耐えられないといったようなこととは関係がない。まったく違う。遥かに深い音楽なのだ。生命を守る特質を備えた音楽というものがある。ここにいる音楽家たちは、音楽によって白人の友人の癌を治してしまったという。わたしはそれを信じる。
実際にこの音楽を聞いてみれば、きっとわかるはずだ……ジュジューカについてとても美しく、同時にとても哀しかったのは、すべての音楽家が残さなければならないものは、彼らの音楽だということだ。つまり、それ以外、彼らには何もないのだ」
■■とても哀しいことについて■■
さきほど引用したバロウズの伝記『リテラリー・アウトロー』について、クローネンバーグはこんなふうに語った。
「まったくブリリアントな本だ。単によくできた伝記というのではなくてすぐれた作品だ。同時にとても哀しい本だと思う。それはバロウズの人生そのものが哀しいものだからだ。その悲しみがわたしの「裸のランチ」にはあると思うけれど、
バロウズの"裸のランチ"にはそれはないかもしれない」
映画「裸のランチ」のラストでは、バロウズが妻を射殺したエピソードが再生される。欠落、喪失にとらわれたクローネンバーグらしいシーンだ。リーは、妻を殺しつづけることによって、作家としての生を生き、書きつづけることになる。
しかし、作家になるということにあまりにも大きな代償が支払われたから哀しみがあるのだと言ってしまえば、この映画は味気ないものになってしまうだろう。
この映画がとても哀しいのは、おそらく、ベンウェイに象徴されるような外的な力と圧倒的な喪失感にとらわれたリーの内的な力が結託して、この映画の冒頭に引用されるハッサン・イ・サバーの言葉のごとく"すべてが許された"王国を作り上げ、いままさにそこに入っていこうとしているからだろう。
目の前で妻を射殺したリーが、アネクシアに入る国境で、警備兵から平然と「ウェルカム」といわれて迎えられてしまうことが、とても哀しいのだ。
|