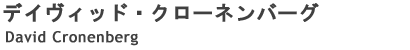|
■■ドクター・ベンウェイ■■
ドクター・ベンウェイは、バロウズ作品の主要な登場人物のひとりであり、小説/映画「裸のランチ」にも登場する。
クローネンバーグの作品には、必ずといっていいほどに医師や医療施設といったものが描かれる。しかも、彼が病院に限らず、なぜか無機的でメタリックで無菌状態に保たれたような空間を好むために、舞台が病院や医療施設でもないのに、病院に見えてしまうような瞬間も多々ある。
彼の作品に描かれる医師や医療施設を列挙してみよう。劇場用映画以前の自主製作作品「クライム・オブ・ザ・フューチャー」に登場するのは、耳や口から体内の分泌物が流れ出す奇病を研究する皮膚病学者。
最初の劇映画である「シーバース/人喰い生物の島」に登場するのは、(表向きは)人体に有益な寄生虫の研究を進める医学博士。「ラビッド」には、交通事故にあった女性に中性化処理した皮膚を移植するという実験段階にある手術をほどこす医師。
「ザ・ブルード」には、患者の意識下にある怒りに肉体的なかたちをもたらす精神科医。「デッドゾーン」の主人公は、病院のベッドで事故による長い眠りから目覚める。「戦慄の絆」の主人公は、双子の婦人科医である。
これだけ並べただけでも、偏執狂的なところがある映画監督であることは十分に感じられるが、クローネンバーグの描く医師には、どこか芸術家じみたところがある。たとえば、「戦慄の絆」で、兄弟の均衡が崩れ出したときに、
弟が、自分で考案/設計した医療器具の製作を文字通りの芸術家にゆだねる場面があるが、これなどは、ある種のクローネンバーグらしさではないかと思う。医師たちは、肉体、あるいは、その内側にイマジネーションをかき立てられ、
肉体を素材に自己主張してしまうような、よくあるマッド・サイエンティストとは一線を画す逸脱を果たしている。
そして、この創造性を備えた医師というキャラクターの枠組みを少し広げると、もう一本の自主製作作品「ステレオ」に登場するテレパシーの実験に取り組む科学者、あるいは、ある薬物の開発によって、
「スキャナーズ」における思考するだけで人間を破壊するスキャナーたちを育成する組織、そして、「ビデオドローム」に登場するメディアを操る教授など、すべての作品を、この範疇に含めてしまうこともそれほど難しいことではない。
「わたしたちは自分の肉体に満足したことがない。わたしたちは、薬や手術で肉体の一部を修正し、自分自身を変身させようと試みてきた。わたしが昆虫に興味がある理由のひとつは、多くの昆虫が成長過程のなかで変身するからだ」というのが、
どうして医師や医療施設を頻繁に描くのかという問いかけに対するクローネンバーグの回答である。
しかし、これは、言わば出来上がった映画の内容や展開にあわせたような優等生的な回答に過ぎない。この監督は、一見論理的な人物のように見えて、実は、実は直観的にものを描いていく作家であるように思える。
彼の映画を観れば、このような回答よりももっと深いこだわりがあることが明らかになるだろう。
映画「裸のランチ」のドクター・ベンウェイは、あまり目立たないキャラクターとして映画に登場し、姿を見せないにもかかわらず、次第に、主人公リーの前に、その存在の影を色濃くしていく。
言うまでもなく、ドクター・ベンウェイは、バロウズ作品のなかで欠かすことのできないキャラクターである。そして、彼の小説でもまた、医師や医療施設が頻繁に描かれる。トニー・タナーは、その著書「言語の都市」のなかで、このことについて次のように書いている。
「バロウズは診断医に転向した麻薬常習者であり、現在は病気の分析に専念している、かつての病人である。彼の作品の非常に多くの場面が、医師、外科医、病院、サナトリウムなどを中心にして展開しているのはそのためだ。
彼の作品のほぼ中核的なイメージは、患者がおそらくいつの日か逃れうる手術台である。彼が病気について警告を発し、その治療の可能性を研究することに努めていることは疑いの余地がない。彼の描く場面の多くが吐き気をもよおさせるような性質のものであるにもかかわらず、
彼は決してセンセーショナルな作家ではなく、アメリカ作家のうちでもっとも冷静で知的で分析的な作家のひとりなのである。結局、彼の場面は視覚的なものではなく、読者は抽象の領域に引き入れられるのだ」
これは、クローネンバーグの世界についても当てはまるところが多々あるのではなかろうか。もちろん、麻薬常習者というところはほとんど関係なさそうではあるが…。
医師や医療施設にこだわるというのは、肉体へのこだわりと置き換えることもできると思うが、たとえば、クローネンバーグに対して、"肉体に対する不信感がある"のではないかというような刺のある質問をしたら、どのような回答がかえってくるのだろう。
「(肉体への関心は)わたし自身の生命に対する観察からきている。人間の生命は肉体なくしては始まらないわけだから、肉体への不信感を唱えているつもりはない。わたしの哲学も肉体からきているからだ。
人間の肉体を探究するということは、人間の情況、状態を探究するということだ。だから、肉体と精神のバランスはとても複雑なものだ。簡単なものではない。だから、肉体への不信という言葉は使いたくない」
クローネンバーグは、ある状況や状態における人間の肉体と精神の複雑なバランスを映画を通して探究している。難解なことのように思えるが、それは素朴な疑問から始まっているのかもしれない。「戦慄の絆」の最初のシーンは、主人公となる双子がまだ子供で、
彼らの会話から始まる。話題は、人間と魚のセックスの違いで、魚もセックスはするが、水のなかにいるために触れ合うことがないといった内容である。しかし、成長した彼らが遭遇する出来事を思い起こせばおわかりのように、素朴な疑問はしだいに複雑な迷宮を作り上げていく。
要するに、クローネンバーグが描くところの医師や医療施設は、一見すると安定しているように見えてひどくうつろいやすい肉体と精神のバランスを浮き彫りにするためにひと役買っているということになる。そして、映画「裸のランチ」で、リーをある情況に導くのも、ドクター・ベンウェイその人である。
■■麻薬中毒、寄生、ウィルス、そして、言葉■■
バロウズは、麻薬常習者としての体験をもとに、個人の体内に侵入し、アイデンティティを剥奪し、完全に乗っ取ってしまうような外的な力を、様々なメタファーを通して描いてきた。
クローネンバーグの作品から、このような伝染するウィルスのイメージを見出すことはたやすい。たとえば、記念すべき劇映画デビュー作『シーバース』。舞台は、医療からスポーツ施設まで何でも完備した高層住宅。
そこに暮らすある医学博士が、娘を実験台に人体に有益な寄生虫の開発を進めていた。実は、彼が本当に寄生虫に期待していたのは、寄生した人体と精神に及ぼす著しい回春効果だったのだが、寄生虫は予想もしない凶暴性を持っていた。
博士が期待した効果によって、寄生虫は人体から人体へと瞬く間に増殖し、独立した高層住宅は、見境のない性の饗宴の場と化していく。この作品は、いまあらためて観ると、AIDSのパロティに見えなくもない。===>2ページへ続く
|