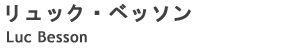 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (初出:キネマ旬報増刊「フィルムメーカーズ1 リュック・ベッソン」1997年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■■荒唐無稽なリアリズム■■ 「ニキータ」は、「最後の戦い」と並んでベッソン作品のなかでも筆者が特に好きな映画である。きわめて荒唐無稽な話でありながら、徹底したベッソン流リアリズムが言葉にしがたいダイナミズムを生み出しているからだ。 この映画は、何よりもニキータというキャラクターが際立つが、筆者は、「グラン・ブルー」のジャックとエンゾと海の関係の変奏が土台となり、そこから最終的に発展したキャラクターのように思っている。ニキータは、 ふたりの男たちと奇妙な三角関係におちいり、一方の男が象徴する、逃れることができない苛酷な現実がのしかかると、闘争本能をむき出しにし、もう一方では愛情に優しく包み込まれるからだ。 この荒唐無稽な設定に対してもちろん、ベッソンはストーリーに沿った流れを作るようなことはしない。彼は、環境や状況の変化とそれに対するヒロインの反応を鋭くとらえることに徹している。空間が激しく歪むことを計算に入れて広角レンズを多用したり、 空間の圧迫感を出すためにカメラを低い位置からかまえて、ヒロインが特別な世界のなかを生きていること、その緊張や孤立感を強調する。 ヒロイン自身に対する演出も際立っている。ベッソンにとって演出というのは、極端にいえば、言葉も使うことなく本能や欲望に忠実に反応したり(「最後の戦い」)、ダイバーに成りきって肉体と精神を改造する(「グラン・ブルー」)というように、 異なる環境や状況に頭ではなく感覚的に反応、順応していくことに近い。そんな演出がこの映画でも徹底している。いくらジャンキーだったとはいえ、それなりに習慣など過去を背負うものだが、このヒロインはまるで別の世界から突然この世界に飛び込んできたかのように、本能的に反応するからだ。 またこれまで触れなかったが、エリック・セラの音楽も、ベッソンと同じように決まったかたちから入るのではなく、感覚的にその空間に溶け込むため、音楽のジャンルやスタイルというものをほとんど意識させない。 こうした映像、演出、音楽が作る世界やドラマがいかにユニークなものであるのかは、アメリカ版リメイクである「アサシン」を観るとよくわかる。展開はそっくりだが、映画は全然違う。「アサシン」はまさにストーリーに沿ってドラマが組み立てられ、 それに少しでも説得力を与えるための平凡なリアリズムが随所に見られる。そんな流れや説得力を無視する「ニキータ」は、「アサシン」に比べると、過剰さやリズムがコミック仕立てに近いが、ベッソン流リアリズムは、それを直接感覚に訴えかけるようなダイナミズムに満ちた、スリリングなドラマに変えてしまうのである。 ■■ベッソンの感性とアメリカの隔たり■■ この「ニキータ」とは対照的に、「レオン」は、ベッソンの監督作品のなかで唯一好きになれない映画だ。物語がカサヴェテスの「グロリア」に似ていたとしても、それがベッソンの世界になっていれば楽しめたと思う。しかしこの映画には、ふたつの世界のせめぎあいから生まれるベッソンらしいダイナミズムが見当たらない。 ベッソン自身は、レオンがリトル・イタリーのような世界でなければ生きられない男だと語り、そこにもうひとつの世界との境界を意識しているようだが、独自の映像がその境界からダイナミズムを引き出しているようには思えない。レオンとマチルダのあいだに家族とも恋人ともいいがたい絆が育まれるところに独自の視点があるという意見もあるだろう。 カサヴェテスは、アメリカ的な作られた家族や愛の絆のイメージをはぎとり、とてつもなく孤独な個人と個人の不協和音のなかに絆を見出してきたわけだが、確かにベッソンがそんな視点を取り込んでみたくなる気持ちもわからないではない。 ベッソンは、いろいろな意味でアメリカに対して特別な感情を抱いているはずだ。これまで海を舞台にした作品を除けば、彼は、もうひとつの世界を構築することによっていつもパリの日常の世界を異化してきた。そうしたもうひとつの世界をさらに突き詰めたところに見えてくるのはアメリカだろう。 ところが彼の特異な感性は、アメリカで必ずしもすんなりと受け入れられてきたわけではない。たとえば、アメリカで最初に公開された「グラン・ブルー」は、音楽をビル・コンティがつけなおし、映像も再編集され、ラストが変えられるという苦渋をなめている。「アトランティス」も94年まで公開されなかった。 「ニキータ」は受け入れられヒットしたが、そのリメイクを見ればいかに感覚が違うのかを思い知らされる。これはもちろん、逆説的にベッソンの個性を物語っているわけだが、もし彼の作品が最初からすんなり受け入れられていたら、「レオン」はもう少し違った作品になっていたようにも思えるのだ。 ■■原点への回帰とベッソンの本質■■ そして最新作となるSF大作「フィフス・エレメント」は、こうしたベッソンとアメリカとの関係を踏まえてみると実に面白い。この映画は最初のほうでも少し触れたように、ベッソンが10代の頃に書いたファンタジーが原作になっている。そういう意味では、荒唐無稽ともいえる独自の世界観が物語の中心にあるわけだが、実際の映画は、様々なレベルでアメリカ的な要素が散りばめられている。 たとえば、この23世紀初頭に設定された未来の世界は、コミックをベースにしたヴィジュアルを前面に押しだし、パロディも含めて「未来世紀ブラジル」や「スターウォーズ」、「ブレードランナー」の要素が入り交じり、ユーモラスな生活感が漂う。はたまた宇宙リゾートでのオペラ公演があるかと思えば、ドラッグ・クィーンのDJのマシンガン・トークが始まるといったように、ハイブリッドなキャンプ感覚に満ちている。 しかし最も印象的なのは、地球の運命の鍵を握る美しい"フィフス・エレメント"リールーとブルース・ウィリス扮するタクシー運転手コーベンの関係である。リールーは、地球にやって来た異邦人であると同時に、アメリカにやって来た異邦人でもある。カプセルに閉じ込められ、謎の言葉を話す彼女に、将軍は、英語を話せば出してやろうと語りかける。彼女はカプセルをぶち破って逃走し、コーベンに助けられる。 その後のコーベンの活躍ぶりはさながら"ダイ・ハード"だが、決定的に違うのは、マクレーン刑事の原動力がアメリカ的な家族の価値にあるのに対して、コーベンの場合は、言葉も通じない異邦人と感覚を共有していくところにある。 この映画のクライマックスを見て筆者がふと思い出すのは、「最後の戦い」の壁画に描かれた世界の再生を暗示するかのような男女のことである。もちろん「最後の戦い」では、ベッソンの喪失感が反映され、そのヴィジョンは現実世界の力によってかき消されてしまった。そこからこのクライマックスにたどりつくまでの変化は振り返ってみると興味深い。 「最後の戦い」でもうひとつの世界を求めながらも現実を受け入れるところから出発したベッソンは、「グラン・ブルー」「ニキータ」で大きな変化を遂げた。この2作品にも喪失感がないわけではないが、せめぎあう世界をめぐるドラマの帰結は重要なものではなくなっている。なぜなら徹底して状況を描くことだけで映画を成立させてしまう独自のスタイルが確立されているからだ。もちろん「アトランティス」もその延長線上にある。 これに対して「レオン」では、アメリカを意識するあまり、「最後の戦い」のように最終的には現実を受け入れざるをえない大枠ができあがってしまっている。先述したように、ベッソン作品のキャラクターというのは、最初から存在しているのではなく最終的に誕生するものである。しかし「レオン」は、これまでの作品から生まれたイメージに依存してしまっているのだ。逆に「フィフス・エレメント」は、娯楽的な要素をふんだんに散りばめながらも、ベッソンの本質が見えてくる。 ベッソンにとって映画というのは、極端な表現をすれば、荒唐無稽ともいえる異質な環境に放り出された人間が、内に秘めた根源的な力によって、どのように生き残り、進化し、最も大切なものを発見するのかを確認する作業に他ならない。そしてそれゆえに、彼の映画からは、見る者の感覚にある種の覚醒をうながすような新鮮な世界が浮かび上がってくるのである。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
