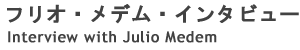 |
||||
|
||||
|
|
||||
| (初出:『ANA+OTTO』劇場用パンフレット、加筆) | ||||
|
|
||||
|
フリオ・メデム監督の『ANA+OTTO』では、8歳のときに運命的な出会いをしたアナとオットーの17年にわたる軌跡が描かれる。奇妙なすれ違いを繰り返すふたりの軌跡を印象深いものにしているのは、まず何よりもアナとオットーそれぞれの視点で語られる物語という構成であり、そして彼らが導かれていく北極圏の神秘的なサークルだ。彼らは、どこからも誰からも遠く隔てられた世界のなかで、孤立した人間としてお互いを求めつづけ、最後に北極圏で再会するとき、彼らの軌跡もまた時空を越えたサークルを形成する。 ――登場人物たちの一人称のナレーションで物語が語られる映画では、監督のスタイルによって、俳優がまずまったくナレーションを意識することなくドラマを演じ、その後でドラマとナレーションが再構成される場合と、最初からナレーションが俳優の頭のなかにはいっていて演じる場合があると思うのですが、『ANA+OTTO』では、俳優たちは、どういうナレーションがかぶるかということを最初から頭に入れていたのでしょうか。 「1ヶ月半に渡ってリハーサルを繰り返し、そのことは頭に入っていました。最初はふたりの主人公だけで始めました。ふたりといっても、時代によって異なる俳優が演じるので俳優の数では6人ということになりますが。それから父親役や母親役の俳優が加わっていきました。毎日、午後になると主人公たちを演じる6人を集めて、ミーティングを行ったのですが、非常に素晴らしい経験でした。このミーティングで大人役の俳優が子供役の台詞を言ってみたり、そういった遊びも盛り込みながら、交流を持ちました。それは、映画のなかに流れを作り出すのに、非常に役立ちました。子供の俳優たちは大人の俳優がどう演じるかを注意していましたし、大人も子供の一挙一動に注目していました。ですので、ストーリーについては全員はっきりわかっていたのですが、子供時代と青春期のふたりは、最終的な結末がどうなるかということを知りませんでした。子供たちのドラマについては、少し衝撃のあるような場面については、われわれが配慮して、具体的に知らせていませんでした。わたしの本当の子供も出演していますが、あの扉の向こうで母親が死んでいるという設定については最後まで伝えませんでした。子供たちの演出については、何らかの物語を発明し、それを有効に活用するようにして演出をしました」 ――初監督作品の『Vacas』には藁人形が回転する象徴的なイメージがあり、今回の映画には北極圏のサークルがあるというように、円とかサークルへのこだわりがあるように思うのですが、そういったものに関心を持つきっかけがなにかありましたか。 「いつ頃ということははっきり覚えてはいません。『ANA+OTTO』については、ストーリーは最初の方から時間の流れにそって書いていきましたが、その半ばにさしかかるまではどういう結末になるのか、自分でもわかりませんでした。主人公たちの青春時代のところで、アナがオットーに向かって地図を示しながら、ここから先が北極圏なのだという説明をする場面がありますが、その場面を思いついたときに、このストーリーはもっと先まで行けるだろう、北極圏のサークルを軸として、話を進めていけるだろうと思いました。それから実際にフィンランドを訪れて、そこではっきりとしました。この映画はフィンランドの場面から始めよう。最後のところから、ふたりがなぜそこに至ることになるかを語る映画にしようと決めました。それで、パートナーとの関係を自分のヴィジョンで語っていくようにしたのです。ふたりの主人公はわたしが創造した人物ですが、彼ら自身にも選択の権利を与えよう。彼らが選んだエピソードを通してどのように愛の運命の終着点に向かっていくか、彼ら自身の言葉で語らせるようにしました。それが愛の理想化であろうと判断したわけです」 |
| |||