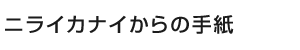 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (書き下ろし) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※『ニライカナイからの手紙』というタイトルがそれを物語っているので、筆者はこのテキストをネタバレとは考えていませんが、ネタバレと思われる方もいるかもしれません。未見の方はくれぐれもご注意ください。 脚本も手がけている熊澤監督が大いなる勘違いをしているのか、あるいは、この映画が、松尾昭典監督の『手紙』につづく"手紙"シリーズ第2弾になるという制約があるためなのかは定かでないが、泣けるどころか、ひどい矛盾を抱え込んだ悲惨ともいえる物語になっている。 沖縄や奄美に伝わるニライカナイとは、海の彼方にある理想郷を意味する。たとえば、松居友の『沖縄の宇宙像』では、それが以下のように記述されている。 「沖縄ではニライカナイは、祖先神の住む島であり、人々のまことの生まれ故郷であると言われる。祖先神たちはニライカナイでこの世の人々と同じ生活をいとなんでいるが、島は桃源郷のごとく美しい理想郷であるとうたわれている。 沖縄の竹富島を舞台にした『ニライカナイからの手紙』の導入部には、海を背景にして、母親がまだ幼いヒロインの風希に、ニライカナイのことを語る場面がある。それを見れば、母親が娘にそうした世界観を伝えようとしているのだと思うし、この映画では、ニライカナイがやがて大きな意味を持つことになるのだろうと思う。ところが、物語は確実にニライカナイから遠ざかっていく。 東京に行ったまま戻ってこない母親からは、風希の誕生日のたびに手紙が届けられる。そんなふうにして風希にとって大切な時間が流れていってしまう。風希が母親を想う気持ちや、母親が娘を想う気持ちがわからないわけではないが、それでは、この手紙は、本当に娘と母親を繋いでいるといえるのだろうか。 もし風希に、もっと早いうちに喪失を受け入れる機会が与えられた場合のことを考えてもらいたい。そうすれば彼女は、その気持ち次第で、ニライカナイからやって来る母親にいつでも会うことができた。そして、文化的な土壌を分かち合い、自分のものにしていくことができた。つまり、東京からの手紙が果たす役割というのは、風希をニライカナイや文化的な土壌から遠ざけ、宙吊りにしてしまうことなのだ。風希はそんなふうにして地元に生きながら、ある意味で根無し草となり、20歳を迎える。そんな物語は、大いなる勘違いというべきだろう。あるいは、風希の運命は、グローバル化する世界のなかで、表層的な感傷に浸っているうちに、文化的な土壌を失っていくわれわれを象徴しているのかもしれない。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||